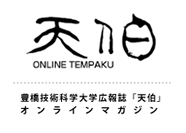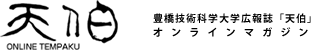特集
もくじ
- 若原新学長を直撃インタビュー!
2025年1月、技科大の卒業生として初めて学長に就任した若原昭浩新学長。技科大の魅力や学生の強み、開学50周年を迎えるにあたっての思いなどをインタビューしました。 - マルチアキシスのダイバーシティに向けて
ダイバーシティ推進センター吉田祥子教授と学生との座談会の様子をお届けします。
Chapter1若原新学長を直撃インタビュー!
2025年1月、技科大の卒業生として初めて学長に就任した若原昭浩新学長。技科大の魅力や学生の強み、開学50周年を迎えるにあたっての思いなどをインタビューしました。
「身近な先輩が学長になったと思って、気軽に話しかけてほしい」と話す学長が考える、これからの技科大とは?卒業生として、学長として抱く熱い思いを語っていただきました。

■学歴■
1990年3月 豊橋技術科学大学大学院工学研究科博士後期課程システム情報工学専攻修了
■専門分野■
半導体工学 / 光電子工学 / 結晶成長
■経歴■
2005年04月 豊橋技術科学大学工学部教授
2022年04月 豊橋技術科学大学理事・副学長
2025年01月 豊橋技術科学大学長
"ほしいモノは自分で作る"が当たり前の幼少期
――幼少期はどのようなお子さんでしたか?
(学長)私は北海道出身で、隣家と離れているような田舎で育ちました。近くのお店で手に入れられるものが限られていたため "ほしいモノは自分で作る。壊れたモノは自分で直す"ということが当たり前の暮らし。物置きにある金槌や鉈、のこぎりを持ち出して日々、モノ作りをしていました。
井戸を掘ったり、浴室を修繕するためにモルタルを塗ったり。父の実家が酪農家だったので、牛舎造りを手伝ったこともあります。必要なモノがあれば、頭と手を使って「じゃあどうする?」と考える。この信念は今も変わらず、私の考え方の核となっています。
――活発な性格でしたか?
(学長)人と話をすることはあまり得意ではなく、おとなしい子どもでした。身体が弱く毎月のように熱を出していたこともあり、本を読む時間が長かったですね。母親にいつも「算数の問題を作って!」とせがんでいたそうです。
――釧路工業高等専門学校に進まれた動機についてお聞かせください。
(学長)モノ作りへの関心に加えて、父親の影響があったのかもしれません。父が趣味で自作した真空管ラジオやテープレコーダーが屋根裏にあったので、トランジスタなどにも興味を抱いていました。電子工学分野が学べる釧路高専を選んだのは、自然な流れだったと思います。

「よく学び、よく遊び、もっと遊ぶ」を実践した学生時代
――進学先として、技科大を選んだ理由を教えてください。
(学長)高専の卒業研究でお世話になった先生が半導体を研究されていて、その授業が非常に面白かったんです。なかでも結晶成長に興味を抱いたのですが、残念ながら北海道には学べる大学がなかった。高専の先生に相談したところ、半導体結晶成長の権威である西永頌教授が豊橋にいらっしゃると聞き、技科大への進学を決めました。
しかし、私が入学するタイミングで西永先生は東京大学へ転籍されてしまっていたという衝撃の事実に直面。一時は落胆して、学ぶ意欲を失いかけましたね。窓越しに見える新幹線をぼーっと眺めながら、通過時刻をノートに書くなどして時間をやり過ごしていました。
そんな時、私を奮い立たせてくれたのは先生や学友との出会いです。技科大に進みたくても入れなかった釧路時代の旧友もいましたし「学ぶべき環境があるのに、無駄にしてはいけない」とモチベーションを高め、学びと向き合う気持ちを取り戻していきました。
――大学時代はどのような学生生活を送られたのですか?
(学長)故郷では当初学校にプールがなく、天然の川で水泳の授業をしていたこともあり、豊橋に来てからも友人を誘って、しばしば川遊びに出かけました。夏になると毎週のように大入渓谷に行って、地元の子どもたちに混ざって岩の上から飛び込んで遊んでいましたね。
ただ学部時代は3学期制だったこともあり、勉強も忙しかったと記憶しています。10週間で1学期が終わってしまうので気を抜く暇がなく、常に授業の復習やレポート課題に追われていました。
研究室時代は、学生の発案を尊重して自由に研究できる体制が整っていたので、自分で計画して実験や解析を行い、振り返るという研究サイクルに没頭。とても刺激があり、充実した日々を送ることができました。
――技科大での学生時代を通して、どのような気付きや学びを得られましたか?
(学長)研究の過程では、計画にないことや定石通りではない考え方こそが、新しい発見や予期せぬ成果につながるのだということを体感しました。
当時の経験から得た私のモットーは「よく学び、よく遊び、そしてもっと遊ぶ」。学びや研究を杓子定規に進めていては、何も生まれない。常に遊び心を大切に、楽しみながら驚きを持って学びと向き合うことで、研究の深度は飛躍的に深まります。
この時に胸に刻まれた信条は、今なお学生たちに向けてのメッセージとして伝え続けています。
――技科大で学ぶことができて良かったと感じたのはどのような点ですか?
(学長)研究室時代、私は3つのグループで実験室を共用していました。そのため結晶成長を勉強している私の隣の席では、別グループの先輩がICやセンサの研究をしているなど混然一体の状況。例えば、当時は自由に使えるコンピューターもまだ少なかったので、突然大きな模造紙が隣で広げられ、配線の立体交差を減らすための考察が始まるわけです。そうすると、専門外の人も含めてワイワイガヤガヤしながら議論が繰り広げられ、自然と幅広い分野の研究に触れることができました。
助手の先生方の部屋も大部屋だったので、担当教授が不在の時には別のグループの先生がコーヒーを淹れてくださって茶菓子を出してくれることもしばしば。「最近どう?」と話を聞いてくださったり、先生の研究談義をうかがったり。
様々な分野の研究に触れる時間、多様な見識を持つ先生方との対話は、自分自身の視野や思考範囲を広げる好機になったと思います。
――学生時代の印象深い思い出があれば、お聞かせください。
(学長)卒業生を送る会では、恒例になっていたグループ全体での温泉旅行です。まだ学生の人数が少なかったこともあり、大型バスをレンタルして全員乗り合いで向かいました。先生も同部屋で寝るので、普段は聞くことができないようないろいろな話ができましたね。
当時の旧友とは今も連絡を取っていて、学長就任の報告をした際もみんな喜んでくれました。50周年を前に同窓会を開くことも決まり、今、日程調整に向けたやりとりが盛り上がっているところです。
また、半導体分野の将来を担う人材育成のために力を貸してほしいという私からの依頼に応え、同級生と後輩が指導者として力を貸してくれています。
母校の学長に就任したことを機に、恩師や仲間とのつながりに対して、改めて感謝の念が膨らんでいます。

これからの学生に求められるのは"ゼロからイチを生む発想力"
――他大学での助手経験もある学長から見て、技科大生の強みやポテンシャルはどのような部分にあると感じられますか?
(学長)理論にとらわれず、疑問や興味が湧いたことはとにかく手を動かして試してみるという点は、技科大の学生ならではと感じます。理論体系やデータがなくても、技術ありきでまずは作ってからデータを収集するという思考回路。これはライト兄弟が飛行機を発明した時と同じアプローチですよね。
偶然できたモノ、予期せず生まれたモノから理論体系を構築していく。モノづくりと理論の両軸で進められることは、最大の強みだと感じます。
――人工知能(AI)やIoTの台頭、DX化が進む中、今後の技科大生に望むことは?
(学長)これからの世の中に求められるのは、AIやコンピューターでは叶わない"ゼロからイチを生む発想力"、"人と人との関係性から何かを生み出せる能力"を持った人材です。
今、知識はデータベースから引き出せますし、解答のある問題はAIが答えてくれる時代です。知識を覚えて単純に答えを出す力は、ある程度必要ではあるものの、おそらくマストではなくなるでしょう。
一つひとつの課題の根底にある問題は何なのかを突き詰め、引き出したデータをどのように組み合わせるかを考える。議論を重ねながら、様々な見地を踏まえてその解決策を探し出す。そうした思考力、考察力、創造力を持った人材の育成が求められていると感じます。
そのためには当然、教員の意識改革も急務です。"教師"という立場から"教える"という感覚ではなく、"ファシリテーター"としての能力を強化する必要があるでしょう。学生が自己探索的な学びを実践できる環境を構築することが、学長としての私の最大のミッションだと感じています。

「身近な先輩」として学生と対話できる関係性の構築を
――2026年10月に開学50周年を迎えます。節目となる年に向けての構想をお聞かせください。
(学長)最初に着手したいのは、学生が研究室を飛び出し、専門分野の垣根を超えて自発的にモノづくりにチャレンジできる環境づくりです。第一弾として、図書館1階に学生の技術交流のための「テック交流スペース」を設置しました。
今後は50周年を機に卒業生らに寄付金も募りながら、環境整備をさらに推し進めていきたいと考えています。
具体的には、例えば3Dプリンターが自由に使える施設などを増やすことで、自発的にハッカソンが生まれ、その場で作って試してデータを分析できるような環境を整えたいと考えています。
学生が面白いと感じたことに躊躇なく取り組める状況、面白がって学べる場を整備すること。この構想には、私自身の学生時代の経験や思い出が大きく影響しています。異なる経験を積んだ学生同士が自由に交流し、多様な見地から共創する。そうすることで新しい発想が生まれてくるのだと感じます。
――最後に現役の学生と、未来の技科大生に向けてメッセージをお願いします。
(学長)学生のみなさんに望むことは、学長として身構えることなく、「身近な先輩の一人」として気軽に話しかけ、どんどん提案をしてほしいということです。もちろん提案を全て叶えることはできないと思いますが、例えば「予算内でできる別の方法はないか」、「考え方を活かして違うアプローチはできないか」と共に考え、対話をしましょう。"可"か"不可か"の二択ではなく、理想に向けて一歩ずつ共に変革していくという関係性を、学生のみなさんと構築したいと願っています。
そしてもう一つ。学生時代には大いに失敗をしてください。何より怖いのは、失敗を経験することなく優等生のまま卒業して社会に出ていくことです。
社会に出ると、失敗が許されない場面も多くなります。失敗を乗り越えた経験のない人は、つまずいた時に一人で抱え込んで悩んでしまい、抜け道を見いだせなくなってしまうかもしれません。
技科大には、チャレンジをサポートする環境も失敗を受け入れる土壌もあります。失敗を避けるのではなく、失敗を次にどう活かすか。その経験こそが将来きっと、自分を支えてくれる方法論につながるはずです。
Q. 趣味は何ですか?
A.ドライブです。人混みは苦手なので、電車旅より車の中の方が落ち着くんです。子ども時代は、クマが出る田舎に住んでいたので、海沿いをおしゃれにドライブするというよりは、木々に囲まれた三ケ日などの山奥を走るのが好きです。
Q. プライベートでもモノづくりをすることはありますか?
A.妻のお父さんから譲り受けた本格的な工具が一式あるので、必要なモノがあればDIYをします。先日も、実家に戻った際に物置の入り口に雨除けの屋根を作ってきました。
Q. 歴史・考古学にも造詣が深いとうかがいました。
A.私の故郷では、化石が出てくることが日常茶飯事でした。学校の裏を流れる川底から木の化石が出てきたり、畑から矢じりなどの石器が出てきたり。リアルな歴史を身近に感じながら育ったので、幼い頃から歴史や考古学には関心がありました。今でも旅先や出張先などで時間が空くと博物館に行くことが多いですね。

お父様から譲り受けた盆栽は、大切に育てているそうです
Chapter2マルチアキシスのダイバーシティに向けて
豊橋技術科学大学では、修学、教育・研究および大学運営等あらゆる場面において、互いを尊重し、多様な人材の個性と能力を、いきいきと発揮できるキャンパスを実現するため、「豊橋技術科学大学 EQUAL」を掲げて、ダイバーシティ推進センターを設置しています。
今回は、学部3年生を対象にした講義「Diversity Tech概論」から見えてきた本学学生のダイバーシティの現状と、あるべき支援の方向性についてまとめたレポートを元に、ダイバーシティ推進センター 吉田祥子教授と学生の座談会の様子をお届けします。
※レポートの内容はこちらからご覧いただけます。

私たちの世代にはダイバーシティは自然なこと
(K)レポートにあるアンケートって、どの時期のアンケートなんですか?3年生?大学に来たばっかりだとわからないことだらけで、不安だよね。質問によっては、不安とかは特に多くなりそうだなって話してました。
(K)そういうバイアスってダイバーシティでもないかもね。
(A)モンゴルではダイバーシティということを聞いたことは全然ないです。モンゴルではダイバーシティとか、宗教的な食べ物の禁忌とか聞いてもらったことがなかったので、日本で聞かれると大事にされているなあと思いました。ひとりひとりの仏教とか色々な意味に尊敬を表している。なんかいいコミュニケーションだと思います。
(H)私たちの世代には、LGBTもADHDも自然に受け入れていたし、学校でも習っている。だいたい男女共同参画法の後に生まれているんです。こんなのがもうだいぶ浸透してきたところから成長してきてるから、大人たちが考えてるダイバーシティと僕たちが感じてるダイバーシティはだいぶ差があるんじゃないかなっていうのを思いましたね。
(M)うん、学校で習ってるから、ダイバーシティがどこに向かうというよりも、自然になってきてるんじゃないかなと思いました。
(K) 高専にもいたもん。
(S)割ともうそんなに気にしてない部分はもともと大きくて、どっちかっていうとそれで過剰に自分を守ろうとする武器にするっていうか、利益を得ようとするみたいなのがあるとそっちに違和感を抱いちゃう。
(K)ノーマライゼーション教育で、学校にいろんな人が入っていて、それが普通のことでもあるし、でもダブルスタンダードは勘弁してほしいというのもある。人間のコミュニケーションってお互いの歩み寄りが絶対に必要だと思う。
(吉田)教育をする大人の立場からは、ダイバーシティであれ、LGBTであれ、そういう人がいるから差別しちゃいけませんよ、サポートしましょうよというのは簡単です。でも学生さんたちが本当に受け入れるためには、何を言ってもらいたいだろう。
(S)自然発生した普通の一個体として受け入れたい。

コミュニケーションの作り方
(A)技科大に入学した時に、国際交流センターの大門先生や、野原先生が、困らない様に大変サポートしてくれて、なんでも聞いてくださいと言ってくれました。逆に日本人は困っていないのですか。
(K)困っている。わからないことがあると、すぐ事務に聞く。
(M)どこに聞いていいかわからない。事務も答えを出してくれない。
(吉田)留学生自体も別にインテリジェンスに困ってるわけじゃない。ただ、日本語はわからないし、日本の市役所とか文化とか、日本人もわかるとは限らない。留学生だってしばらくして馴染んできたら、自分でいろいろ勝手にやりたいじゃない。だから困ったときはいつでも来ていいけれど、困るまで来なくていいよっていうのが本当はいいサポートなのかな。
(S)ニュースとかで、海外の人が盗んだ、外国人ってやっぱやべえみたいなのが流れる時があるんですよ。別に日本人も盗むんですけど。そういうのの原因が、もしかしたら伝言ゲームみたいなディスコミュニケーションかなと思うんです。
(K)だったら、留学生もダイバーシティも、異文化交流がその自分の身を助けるんじゃないかな。英語勉強するサークルあったよね。
(M)国際交流サークル、動いてる。すごい元気だけど、日本人はあんまりいない。
(K)学生は若いから、日本英語わかんなくても参加していい留学生と交流するお茶の会みたいなイベントがあると、授業よりコミュニケーション取れるかな。
(S)先日、ダイバーシティ活動でやった座談会みたいな、気楽な内容でラフにわちゃわちゃしながら遊びに近いような会で、みんな楽しんで参加するのがいい。

高専出身者が多い本学の特徴
(S)高専出身者って得意教科が尖った学生なんですよ。あと経済的に恵まれてなくて、技術を磨きたいっていうよりかはいい会社に就職したいとか経済的に苦しいとかで高専を選んでる。
(M)3年生で内部進学と合流した時、まずいろいろ声かけましたね。でも本当にいろんな学生がいる。
(K)アンケートを見ると高専生だなって思いました。オタクっていうのも定義が最近広くなっちゃって、いい意味で捉えられている部分も増えてきたので、一極集中型のオタクだけじゃない人も、自分はオタクだって言える雰囲気に今なってる。オタク気質とADHDの相関には、だからちょっとノイズがあるんじゃないかなと思う。本物のADHDのひとは自分の性質に気づいてない、興味ないって、なるんじゃないかな。
(S)一方で、高専生って変なやつが多いとか、ADHDが多いっていう情報を聞いて、自分もそうじゃねえのって意識的に変わっちゃった可能性はあるかな。監視と囚人実験みたいな、言われたらそっちに寄ってしまうっていうのは絶対あると思う。それで幸せに生きていけたらまあいいかなとは思う。
(H)僕らはもうADHDっていう言葉ができて、ある程度その像ができて、ある程度自分で理解してる世代じゃないですか。じゃあ、大人の世代ってどうだったんだろうっていうのを一回聞きたくて、そもそもそういう言葉とかそういう像がなかった時に、そういう人たちはどうしてたのかな。
(吉田)大人はその差別からも抜けておらず、共存にも達してないかもしれないね。
今日はありがとうございました。