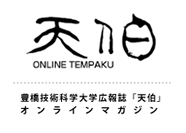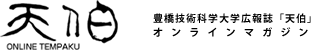輝くギカダイ卒業生
もくじ
- 自分でコントロールできることを 自分の頭でよく考え、 やれることを実行する。 失敗を恐れずにチャレンジしてほしい。
1982年3月 旧電気・電子工学専攻 修士課程修了 株式会社日本マイクロニクス エグゼクティブアドバイザー 木下 嘉隆(きのした よしたか)氏
Chapter1自分でコントロールできることを 自分の頭でよく考え、 やれることを実行する。 失敗を恐れずにチャレンジしてほしい。
1982年3月 旧電気・電子工学専攻 修士課程修了
株式会社日本マイクロニクス エグゼクティブアドバイザー
木下 嘉隆(きのした よしたか)氏

1982年 株式会社 日立製作所入所
1999年 同社半導体事業本部DRAM事業部開発部部長
2000年 エルピーダメモリ株式会社(NEC日立メモリ株式会社)に出向その後、転籍し、執行役員、取締役、社長を歴任
2014年 社名変更により、マイクロンメモリジャパン株式会社 社長となる。
(現マイクロンメモリジャパン合同会社)
2020年 株式会社日本マイクロニクス エグゼクティブアドバイザー就任
■大学入学前は、どのような子ども・学生でしたか?
子どもの頃は、プラ模型作りが大好きでした。学業は、小学生の頃は5段階評価のオール3の成績。しかし、田舎の中学に転校したことが私のやる気スイッチをONにしてくれました。また、その時期に柔道部に入部し、その後、高専の武道の授業では剣道を選択して、柔道と剣道両方で初段を取得できたことは、ビジネスや会食で海外の人と話す際の話題にもなり、良かったと思っています。
■豊橋技術科学大学への入学を志望した理由は何ですか?
これからの時代は"電子"だ、高専では勉強できないが固体物性やら半導体がおもしろくなりそうだと直感的に思いました。ちょうどこの頃に技術科学大学が豊橋と長岡に開学し、私の学年が一期生として受け入れてもらえると先生から伺いました。経済的にはとても厳しかったので親に相談をし、奨学金貸与やアルバイトなどを前提に進学させてもらいました。また、先生からは半導体を学びたいなら豊橋技科大が良いと勧められ志望しました。
■ 豊橋技術科学大学で学んだことや印象に残っていることは何ですか?
技科大での研究室配属では迷わず電子デバイス講座を希望し、真新しい出来立ての研究室の大部屋に受け入れていただいたときのことを今でも覚えています。技科大の電子デバイス講座が私の半導体キャリアの原点となっています。

一期生の苦労とメリット、両方をエンジョイしました。何もないところから作り上げていくことができたこと、先輩や先例がないので自由にできたこと、 開拓者精神のようなものを学ぶことができたと思います。社会人になると教科書に書いていないことがたくさん起こります。その際に、開拓者精神はとても重要だと思いました。
特に大学生当時、集積回路ができる日本一(だと思うレベル)のクリーンルームを立ち上げた苦労・経験は社会人になってからとても貴重なものになっています。和の精神から私のリーダーシップというものが出来上がったのだと思います。
■ 仕事でのやりがいや、仕事をする上で大切にしていることを教えてください。

好きなことを仕事にできたことがやりがいでもあり、その結果、長続きすること(38年間)ができたと思います。これは本当に幸運でした。「幸せ」の反対は「不幸」ではなく、「退屈」であると聞いたことがあります。半導体メモリ事業の38年間は良くも悪くも私を本当に退屈にさせてくれませんでした。今、振り返ってみると、大学を卒業してから退職するまで本当に幸せな会社 生活を送ることができたと思います。
エルピーダメモリが会社更生法申立てをした際、同社の技術力を信じ、技術力が無くて倒産したのでは無い、絶対に技術力で再建できるという信念を持てたのも、心底DRAM(Dynamic Random Access Memory)が好きでやってきたことだったからだと思います。
■学生に向けたメッセージをお願いします。
「成功の反対は失敗ではなく、何もしないことである」、これは何かの本で読んだ受け売りですが、私の好きな言葉です。若い皆さんには失敗を恐れずにチャレンジしていただきたいと思います。また、自分でコントロールできないことにくよくよ悩まない。何が自分でコントロールできて、何ができないのか、自分の頭でよく考え、自分でコントロールできることに集中し、やれることを実行する。多少の鈍感力も必要かもしれません。
子どものころオール3の平凡だったため、母親から成績が優秀な人はどこが素晴らしいのか、どうしたらそうなれるのかをよく観察して少しでもそのように真似してみなさいと言われてきました。人の良い点、優れた点を見て欠点をできるだけ見ない性格は社会人になってからとても役に立ちました。自分一人ですべてに秀でる必要はない。世の中には自分より優れた能力を持った人がたくさんいます。能力やスキルの足りない部分は、それを持っている人を探し出してきて、プロジェクトに参加してもらって助けてもらえば良いのです。
どんな人にも必ず良い点、優れている点があります。好き嫌いは横に置いておいて、良い点、優れている点だけを的確に観察する力を身に着けることをお勧めします。