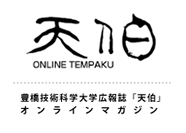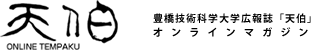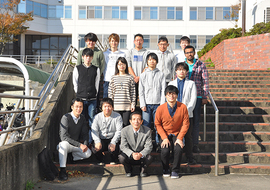退任教員挨拶
もくじ
- 「転石苔を生ぜず」
機械工学系教授 北村 健三(きたむら けんぞう) - 研究生活を振り返って
情報・知能工学系教授 堀川 順生(ほりかわ じゅんせい) - 20年を振り返って
環境・生命工学系教授 平石 明(ひらいし あきら) - 技科大29年間の思い出
建築・都市システム学系教授 松本 博(まつもと ひろし) - 理論・実験・大学での37年
総合教育院教授 鈴木 新一(すずき しんいち)
Chapter1「転石苔を生ぜず」
機械工学系教授
北村 健三(きたむら けんぞう)
昭和54年4月にエネルギー工学系助手として赴任して以来、38年の長きに亘り本学にて教育・研究に従事させて頂きました。この間、先輩や同僚の先生方から様々なご指導、ご厚誼を頂きましたこと、心よりお礼を申し上げます。また、研究室を巣立っていった多くの学生諸君と共に楽しく有意義な時を過ごせことに、感謝致します。
本学に赴任したのは、本学の1期生が学部4年次に進学し、卒業研究を始める時でした。私の所属した熱工学研究室には、斉藤武先生、三田地紘史先生が既に居られました。斉藤先生は副学長職でお忙しいこともあって、Drコースを修了したばかりの私にも何人かの卒研生の研究指導が任されました。
どのような研究テーマが良いか一生懸命考えましたが、悲しいかな当時の私は能力不足で良いテーマが思い浮かびません。仕方なしにひねり出したテーマで卒研をすることになりましたが、そのような状況でも、学生は朝早くから夜遅くまで熱心に実験に取り組んでくれました。
本学創設当時の学生の研究にかける意欲や能力は、旧帝大の学生に比べても決して遜色が無かったように思います。そのような恵まれた環境で学究生活を送れることに無上の喜びを感じ、ついつい本学に長居をしてしまいました。
それから三十数年の時が立ち、漸く何を研究すべきか、何が世の中の役に立つ研究かが少し分かる歳になって来ました。しかし、それが分かる頃には色々な意味で時すでに遅しという訳です。私の例を引くまでもなく、若い研究者が一人前の研究者に育つには多くの時間と経験が必要です。今のように、若い研究者に成果を急がせるのか、昔のようにじっくり育てる方が良いかは、人により様々な意見が有るかと思いますが、大変難しい問題です。
表題に掲げた諺「転石苔を生ぜず(A rolling stone gathers no moss)」にも相反する2つの意味が込められています。英国では苔が生えるのは良い意味に、米国では悪い意味に捉えられています。どちらが正しいか判りませんが、私に苔が生えたことだけは確かなようです。
最後になりましたが、非力ながら充実した大学生活を過ごせましたこと、感謝申し上げます。我が豊橋技術科学大学の益々のご発展をお祈り致します。
Chapter2研究生活を振り返って
情報・知能工学系教授
堀川 順生(ほりかわ じゅんせい)
1998年に本学に赴任し、19年間お世話になりました。本学に赴任する前は東京医科歯科大学難治疾患研究所で19年間、動物を使った聴覚の研究を行っていました。医学部から工学部へ来たきっかけは、旧知識情報工学系の教授公募に応募したことでした。もともとは大阪大学基礎工学部出身で、研究ではミニコンピュータを使用していたので、工学部での教育・研究には特に問題はありませんでした。赴任後、防音室や計測機器などの実験用設備の立ち上げに数年間かかりました。この間は難治疾患研究所と共同研究を行い、学生を派遣して実験を行なったりしていました。
設備が整ってからは、本学での研究が順調に進み始めました。動物実験と並行して、人の脳波の計測も始めました。最近、新田恒雄本学名誉教授との共同研究で、言葉を脳波から読み取ることができるような結果が出てきました。
本学に赴任して数年後から大学の教育改革が始まり、十年以上にかけて学内再編や法人化などの対策に追われました。しかし、この改革は何であったのかと思われるほど、大学の教育・研究環境は変わっていません。これらに費やしたエネルギーが研究につぎ込める環境であったらと思ったりもします。
本年度は情報・知能工学系JABEE対策委員長と国際会議の大会長が重なり、大変忙しい年でした。JABEE実地審査は11月初めに行われ、無事終了しました。国際会議は12月中旬に田原市の伊良湖シーパーク&スパホテルで開催しました。会議内容や会場などについて参加者からの評判がよく、成功でした。
総合的に本学での教育・研究生活は楽しいものでした。いくつかの研究は未完成となりましたが、退職後も時間をかけてまとめたいと思っています。最後になりましたが、これまでにお世話になった方々に感謝申し上げます。また、豊橋技術科学大学のますますのご発展をお祈り致します。
Chapter320年を振り返って
環境・生命工学系教授
平石 明(ひらいし あきら)
私は今から20年前に民間から本学へ赴任してきました。退職を前に、これまで私の目に映ってきた周囲の変化を簡単に振り返ってみたいと思います。
まず本学の官舎の周囲にそびえ立つ松の木やクスノキに深い印象をもちました。例年7月からこれらの樹上で鳴くクマゼミの大合唱を聴くことができますが、初鳴きの時期は年を追って早まっており、この20年で2週間も早くなりました。残念ながら多くの樹木は伐採されるか枝を深く切り落とされてしまったので、これからはこの風情を感じることもなくなるでしょう。
本学キャンパスには研究棟や講義棟を中心に初夏に沢山のツバメが営巣します。しかしヒナ巣の数は20年前の50%以下まで減少しました。
キャンパス内には野ウサギやキジやアオダイショウが割と頻繁に見られましたが、年々目撃回数は減り、この一年で目撃できたのは野ウサギ1回だけに留まりました(写真1)。
キャンパス北側から運動場にかけては秋になるとナンキンハゼの美しい紅葉が見られます(写真2)。しかし、最近では紅葉の時期が極端に遅くなったり、紅葉というよりは枯れ葉のような色づきになることが多いようです。
本能的に生きる動植物はこのように環境変化に対してきわめて敏感に応答し、そこにはごまかしはありません。
一方で大脳皮質を進化させた人間は生物学的感覚が劣化し、その言動にはしばしばウソがあることは皮肉なことです。
昨今ではフェイク情報が氾濫し、自分にとって都合のよい情報だけにしか関心がないような傾向もみられます。電脳時代を生きる今こそ、あらためて自然からのつぶやきに耳を傾け、五感を研ぎすますことも必要ではないでしょうか。
また、すっかり消えてしまったキャンパス内の水辺が復活することも望みたいものです。
最後に、大学の自由な雰囲気は何事にも代え難いものであり、このようなことを考えられる時間を与えていただいた本学に対して深謝するとともに、本学のますますの発展をお祈り申し上げます。
Chapter4技科大29年間の思い出
建築・都市システム学系教授
松本 博(まつもと ひろし)
私は昭和63年4月に東北大学から本学に講師として着任しました。その前年に旧建設工学系教授の本間先生に声をかけていただいたのがきっかけです。昭和64年が昭和天皇ご逝去でわずか1週間しかありませんでしたので、実質的には昭和最後の年です。その後、助教授を経て今から11年前に教授に昇任、現在に至っています。在任29年間を振り返ると、いろいろな思い出がありますが、どちらかと言うと辛かったこと、失敗したことの方が強く印象に残っています。
その中で一番辛かった思い出は、4年前の故山田先生のご不幸に直面したときです。当時系長として系会議の場で教職員に訃報を報告したときには、不覚にも涙が溢れて言葉になりませんでした。山田先生とは大学が同窓で長年助手として同じ教育現場にもいましたので、本当にショックでその後の系の運営を果たしてうまくやっていけるどうか、途方にくれたこともありました。そのとき、支えになってくれたのが系のスタッフでした。非常に献身的に系の業務や学生のケアをしてくれました。このときほど人の絆の有難さを感じたことはありません。
在任中に感じた本学の良さの一つに、人と人との距離がとても近いということではないかと思います。私は着任以来、第2代学長の本多波雄先生に始まり、現学長の大西先生まで6代の学長との出会いがありましたが、これほど学長先生との距離が近く、またじっくりと直接お話できる大学は他にないのではないでしょうか。
私は研究面では必ずしも納得できる成果が得られたとは思っていませんが、講義等の教育面では手を抜かず全力でやってきた自負があります。現役最後の国際プログラムの講義で留学生から感謝と一緒に集合写真を撮りましょうと言われたことは、これまで真摯にとりくんできた教育が多少報われた気がして正直とても感激した思い出があります。これまでの幸せな29年間に感謝しつつ、今後の豊橋技術科学大学の益々の発展をお祈りします。

Chapter5理論・実験・大学での37年
総合教育院教授
鈴木 新一(すずき しんいち)
中学1年の時、理科の授業で水の電気分解の実験がありました。陰極から発生する水素を試験管で集め、火をつけると「ポン」という音を立てて燃えます。水素の量が少ないうちは音が小さいのですが、水素の量が増えてくると「ポン!!」という大きな音をたてて燃えます。さらに水素の量が増えて試験管の中の空気を追い出してしまうと、水素は燃えにくくなり、音はまた小さくなります。この授業では、水の電気分解と水素の燃焼を原子論から説明し、また原子論から予想される結果を実験によって実証していました。
この実験は12歳の私に、「理論と実験で世界は理解可能である」という強い印象を与えました。そして、それまで日常生活に埋没していた少年の世界は、これを境に一変しました。「水中の魚が水面から顔を出すことにより、外の世界があることを、そして、自分がそれまで水中にしかいなかったことを初めて知る」という例え話がありますが、まさにそのようなものでした。
やがて「大学で仕事をしたい」と思うようになり、1980年4月から本学に奉職することとなりました。本学では主に、「破壊力学の理論を実験的に検証する」研究を進めてきました。破壊力学は船や航空機、橋や堤防などの社会基盤を破壊から守り、社会の安全を保障する目的で発展してきました。静かな大学の研究室で、「実験による理論の検証」という最も基本的な科学的活動に携わっている時は、学問とその安全保障への寄与を肌で感じられる瞬間でした。
私たちは、どの時代のどの場所に生まれてくるかを選択できません。そのため、生まれ育った土地の因習や時代の風潮から自由になるための視座を、常に必要としています。大学はそのような視座を若い人々に提供するのに最も相応しい場所であり、その様な場所で37年間研究できたことは大変幸福でした。あらためて御礼申し上げます。ありがとうございました。

左から足立忠晴教授、筆者、秘書の村井麻葉さん