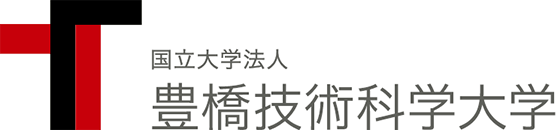4月1日に大西隆新学長の就任挨拶を行いました。
イベント報告 | 2014年4月 2日
 |
|||
|
就任挨拶をする大西学長
|
|||
 |
|||
|
就任挨拶後の新執行部の紹介
|
|||
 |
|||
|
出席者のようす
|
4月1日に、本学A-101講義室にて大西隆新学長の就任挨拶が行われ、202名の教職員及び学生が出席しました。
就任挨拶では、大西学長の大学運営と教育・研究に関わる基本的な考え方を述べられた後、①大学全体のグローバル化の一層の推進、②大学と地域社会との連携、③研究面での本学の優位性の更なる構築、④教育面でのグローバル人材育成の推進、⑤管理運営体制の改革の5つの目標を掲げ、本学をさらに飛躍させるための決意を述べられました。
大西学長の就任挨拶は以下のとおりです。
技術科学のグローバル化-豊橋技術科学大学の挑戦
2014年4月1日
学長 大西 隆
4月1日から学長に就任した大西隆です。豊橋技術科学大学が目覚しい活躍を遂げ、社会からも大きな期待が寄せられている時に、本学の学長になったことをとても嬉しく感じるとともに、舵取り役の重責に身の引き締まる思いです。
ご存知のように、世界をリードしてきた我が国の産業技術と基礎的な技術科学研究の持つ国際競争力の将来に対して、特に産業界では危機感が強く、総合科学技術会議等でも大学に対する期待とともに、解決するべき課題が多いことを厳しく指摘しています。文部科学省も国立大学改革プランの策定などによって、基礎的技術科学研究や人材育成を担う大学に大きな変革を求めています。このような状況下で豊橋技術科学大学をさらに飛躍させるために、就任に当たって、大学運営と教育・研究に関わる基本的な考え方を申し述べます。
まず、榊佳之前学長が手がけてこられた大学運営、教育・研究に関わる多くの優れた事業を継承して、発展させていく所存であることを申し上げます。
教育では、長岡技術科学大学、国立高等専門学校機構と連携した三機関が連携・協働した教育改革事業が動き出し、本学は海外教育拠点(ペナン校)を活用したグローバル指向人材育成事業を担当しています。さらに博士課程教育リーディングプログラムも始まりました。
研究では、昨年研究大学強化促進事業の支援対象22機関の1つに選ばれ、研究環境の一層の充実に取り組むことになりました。また大学運営については、トップダウンとボトムアップを組み合わせた全学的コンセンサスに基づく運営体制が指向されてきました。これらをはじめとする諸事業は、いずれも、我が国の国立大学としては先進的な試みであり、さらに発展させていきます。
その上で、国立高等専門学校(以下、高専)本科卒業生が多数学ぶことを特色とする本学をさらに発展させて、工科系大学として世界のトップクラスに列せられるようになるために、私は以下の点を目標として、教職員とともに、不断の改革と前進を図る所存です。
第1に、大学全体のグローバル化を一層進めます。日本社会のグローバル化が進んでいますが、大学はその最前線に立たなければなりません。大学改革プランでも取り上げている教育・研究のすべての分野における活発な国際交流が進むように、キャンパス全体の多文化共生化を進めます。
第2に、大学と社会との連携、とりわけ大学の持つ資源を社会の発展のために有効に活用していくために、地域社会の皆さんと多チャンネルでの交流を進めていきます。
特に、この地域は、南海トラフ大地震による被害が心配されているため、地域の拠点として、防災・減災をはじめとする安心・安全な社会の形成に貢献していきます。
第3に、研究における本学の優位さを高め、層を厚くします。既に「LSI工場」をベースにした高感度センサーチップの開発、超高密度超高速光メモリーの開発の実績を踏まえ、エレクトロニクス先端融合研究所を設立しました。融合研究は、イノベーション創出にとって極めて有効な手段であり、この研究所の活動を一層盛り立てていくとともに、他の分野においても、学内外の研究者との共同研究を通じて、より高いレベルの研究力を持つことを目指します。さらに、それらを支える個々の基盤研究と合わせて、研究における重層構造を形成するよう力を注ぎます。
第4に、教育においては、長岡技術科学大学・高専との連携の下で、グローバル社会におけるコミュニケーション能力を備えた人材育成を進めます。高専本科卒業生を創造的な高度技術者に育成する本学のミッションを更に強化するため、昨年発足させたペナン校を拠点に、学部・博士前期課程を連続して展開する課題解決型長期インターンシップを創設し、グローバルに活躍しイノベーションを起こす技術者の育成を推進します。さらに、教員の英語での講義実習も進め、本学の教育におけるバイリンガル化を進めます。加えて、より多様な国々から、より多数の留学生に本学で学んでもらえるよう、留学しやすい大学づくりを目指します。
第5に、管理運営においては、人材の継続と流動という一見対立する課題を統合させる制度改革に挑みます。研究環境を向上させることによって優れた研究者が本学で継続的、安定的に研究できるとともに、研究の進展に応じて、流動性を確保することによって、新しい刺激が本学に与えられるようにすることが重要です。また学内の運営では、大学の現状と課題について皆が情報共有し、執行部の意思決定に共感してもらえる環境を整えます。
その第一段階として、各系長に大学の管理運営等に関する重要事項の企画、立案等を行う会議の構成員になって頂き、大学運営をともに論ずる体制としました。
そしてこれらの目標を達成する上で、最も重要な点は、大学は、本来、学問を学び、深める教育と研究の府であるという原点に立ち返って、自由闊達に語り合え、ひらめきに応じて思うままに研究できる環境を整えて、教育と研究の喜びを享受できるようにすることが重要です。そのためには、教員、職員、そして学部学生・大学院生が互いに助け合いながら、知的なキャンパスライフを充実させていくことが不可欠です。是非、そうしたキャンパス形成に努力していきます。