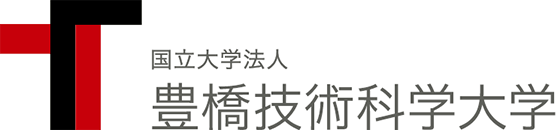平成25年度テーラーメイド・バトンゾーン教育プログラム「開発リーダー特論 第4講義」を開催しました。
イベント報告 | 2013年7月 8日
 |
| 講演の様子 |
 |
| 講演の様子 |
7月4日に、(株)日立システムズ 技監(兼)東京大学大学院情報学環(特任)教授の井村亮氏を講師に迎え、平成25年度テーラーメイド・バトンゾーン教育プログラム「開発リーダー特論 第4講義」を開催しました。
今回の講義は、「世界最小の無線認識IC・μ-Chipの開発と事業化への挑戦」と題して、日立が開発したRFID μ-Chipの社会実装をめざし、如何に市場開拓および新事業創生に取り組んだかその過程について語っていただきました。
電波を用い非接触でデータキャリアーを認識する個体認識技術であるRFID μ-Chipは、それまでのバーコードに代わる次世代の固体認識技術としての強い期待はあったが、事業展開を考えるにあたっては、RFID μ-Chipでなければできない応用とは何かをよく考え、紙にすき込むタイプの2001年日本万国博覧会入場券への適用を皮切りに、パスポートセキュリティ、食品製造品質管理、火災警報器ネットワーク、原子力発電所用誤配線防止電気ケーブル、工具管理等、広範囲にわたる応用展開を進め、成功を収めたとのことでした。
しかしその一方で、結局はモノにならなかった数多くの失敗も経験されました。しかし後になって考えてみると、その失敗の経験があったからこそ、起業成功のために本当に必要な作戦と戦略を学びとることができたとのことでした。煎じ詰めれば、それは真のニーズに裏付けられた市場はあるか、リスクを背負ってでもそれに投資できるか、コア技術を持っているか、重要な意思決定を自ら下せられるか、と言うことだと話されました。
最後に、組織が生き続けるためには絶えず新しい分野を切り拓く活動が必須であり、その意味で、研究・開発こそ
「Engine of Tommorow」であり、失敗を恐れず、何事にも自ら挑戦していくことが大切であると訴えられました。研究に没頭する毎日の学生たちにとって、研究成果を世の中に実装し、ビジネスにするとはどういうことか、そのプロセスを知る良い機会でした。