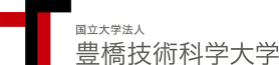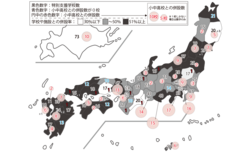亀屋 惠三子(かめや えみこ)
研究紹介
マイノリティーの方を取り残さない生活環境を研究しています。建築とは公共物としての役割が大きいものもあり、平均的、あるいは一般的な特性が重視されることは必然ではあります。しかしながら、様々な人の特性を平均化したものが一般的とされているとしたら、それはだれにとっても何となく使いやすいものであると同時に、だれにとってもちょっとずつ使いにくいものを作ることを意味します。マイノリティーの方を取り残さない生活環境は、誰かの不便を受け入れる我慢や寛容さ、平均という名の不在の人々ではなく、特定の「誰か」にきちんと届くものであってほしい。「一般」というものが独り歩きせず、それぞれにとって快適な空間を創造できることを目指しながら研究しています。
テーマ1:SDGsの生活環境
概要
貧困支援のための施設や障害児・者の教育環境、不登校児童・生徒の教育環境、難病者の生活環境などを研究してきました。どの人々も、どの環境も一般解ではなく、特別解として扱われる施設環境です。特別な人だから・・・・という言葉で片づけることなく、どうしたらフラットな環境を提供できるかを考えながら研究しています。特別な人たちに特別な環境を用意することは「配慮」していることになるのでしょうか。社会全体として考えていかなければならない難しい問題だと考えています。
主な業績
1)亀屋惠三子、「在宅介護を行ったALS患者遺族の過ごし方と住まい方の変化に関する事例的研究」、日本家政学会誌No.70(7)、pp.425-436、2019.7
2)亀屋惠三子、大野真太郎、松田雄二、「救護施設における空間特性と利用者の生活環境に関する研究(その1):新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大期(緊急事態宣言下)における諸室の使われ方や過ごし方の変化」、日本建築学会計画系論文集No.86(787)、pp.2223-2233、2021.9
3)亀屋惠三子、深澤彩花、古賀政好、山田あすか、「小学校・中学校・高等学校と併設する特別支援学校の特性と交流活動・施設共有に関する研究、日本建築学会計画系論文集No.88(811)、pp.2476-2486、2023.9
キーワード
テーマ2:医療施設の建築計画史に関する研究
概要
今は存在していない結核療養所の空間構成について研究しています。
まだ医療技術や建築技術が発達していない時代の古い建築図面を分析しながら、昔の人の療養環境を分析しています。新型コロナウイルス流行時には、手洗いやソーシャルディスタンスが励行されましたが、歴史を紐解いてみると結核の流行時もまた、国家対策としてそれらが行われていることがわかっています。コロナ禍の「新しい生活様式」は、新しくなかった…ようです。古い資料を読み解きながら、当時の生活様式と建築を洗い出しています。
温故知新とは言いますが、近年は科学技術の目覚ましい進歩により、時代の流れが速く、古きを温めることなく進んでいるように思えます。アーカイブ研究は、それらのベンチマークとなりうる可能性を秘めています。
主な業績
1)亀屋惠三子、境野健太郎、「近代期における結核療養所の建築計画史に関する研究(その1):時期別にみる設立主体と建築特性、日本建築学会計画系論文集No.88(804)、pp.392-403、2023.2
キーワード
担当授業科目名(科目コード)
学部座学:設計序論(B15530050)、建築計画(B15621050)
学部設計:建築設計演習Ⅰ(B15510130)建築設計演習Ⅳ(B15621080),建築設計演習Ⅵ(B15621160)
大学院座学:建築デザイン特論(D35030040)
その他(受賞、学会役員等)
【受賞】
1)2006年、住宅総合研究財団 研究奨選
2)2007年、日本建築学会 奨励賞
3)2014年、住宅総合研究財団 研究奨選
4)2020年、日本家政学会中部支部 論文奨励賞 など
【役員など】
社会福祉法人 理事(2025.5~)