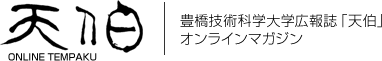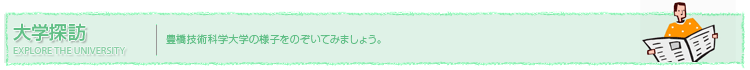
もくじ
クリックすると各記事の先頭に移動できます
クリックすると各記事の先頭に移動できます
新任教員紹介
- 横山博史(よこやま ひろし)/機械工学系 助教
- 永井萌土(ながい もえと)/機械工学系 助教
- 武藤浩行(むとう ひろゆき)/電気・電子情報工学系 准教授
- 栗本宗明(くりもと むねあき)/電気・電子情報工学系 助教
- 関口寛人(せきぐち ひろと)/電気・電子情報工学系 助教
- 田上英人(たのうえ ひでと)/電気・電子情報工学系 助教
- 平野雅嗣(ひらの まさつぐ)/情報・知能工学系 准教授
- 大村 廉(おおむら れん)/情報・知能工学系 講師
- 増田幸宏(ますだ ゆきひろ)/建築・都市システム学系 准教授
- 辻子裕二(つじこ ゆうじ)/建築・都市システム学系 准教授
- 山本 綾(やまもと あや)/総合教育院 講師
- サンドゥー アダルシュ(SANDHU Adarsh)/エレクトロニクス先端融合研究センター 教授
- 鯉田孝和(こいだ こうわ)/エレクトロニクス先端融合研究センター 特任准教授
- 沼野利佳(ぬまの りか)/エレクトロニクス先端融合研究センター 特任准教授
- テイエテイエルコブ ズミトリー(Dzmitry Tsetserukou)/エレクトロニクス先端融合研究センター特任助教
- 三澤宣雄(みさわ のぶお)/エレクトロニクス先端融合研究センター 特任助教
編集部だより

横山博史(よこやま ひろし)/機械工学系 助教
 平成22年4月に機械工学系に着任いたしました。これまでの研究は、新幹線や自動車などのまわりの流れから発生する風切音(空力騒音)について行ってきました。流れから音が発生する様子をコンピュータで可視化して、音を小さくするにはどうすればよいか?といった問題に取り組んできました。これからも、本学の充実した設備を利用し、研究に精進したいと思っています。これまでは関東に暮らしていて愛知で暮らすのは初めてなのですが、伊良湖岬など景色が良い所が多いようなので、休日にはいろいろ回れたらと思っています。
平成22年4月に機械工学系に着任いたしました。これまでの研究は、新幹線や自動車などのまわりの流れから発生する風切音(空力騒音)について行ってきました。流れから音が発生する様子をコンピュータで可視化して、音を小さくするにはどうすればよいか?といった問題に取り組んできました。これからも、本学の充実した設備を利用し、研究に精進したいと思っています。これまでは関東に暮らしていて愛知で暮らすのは初めてなのですが、伊良湖岬など景色が良い所が多いようなので、休日にはいろいろ回れたらと思っています。


永井萌土(ながい もえと)/機械工学系 助教
 4年ぶりに出身の愛知県に戻ってきました。出身は愛知県江南市です。豊橋からは、名鉄特急で約1時間の距離です。赤だしや三河弁で愛知にいることを実感します。微生物を使ったマイクロシステムを構築する研究をしています。微生物や作製したデバイスを顕微鏡で観察しては、一喜一憂する日々です。研究で頭を動かすのはもちろんですが、自転車に乗ったり、トレーニングジムで筋トレしたりと、身体の方もよく動かしています。今後は、教育と研究を両立し、自分も学生もレベルアップして、技科大を盛り上げていきたいと思っています。
4年ぶりに出身の愛知県に戻ってきました。出身は愛知県江南市です。豊橋からは、名鉄特急で約1時間の距離です。赤だしや三河弁で愛知にいることを実感します。微生物を使ったマイクロシステムを構築する研究をしています。微生物や作製したデバイスを顕微鏡で観察しては、一喜一憂する日々です。研究で頭を動かすのはもちろんですが、自転車に乗ったり、トレーニングジムで筋トレしたりと、身体の方もよく動かしています。今後は、教育と研究を両立し、自分も学生もレベルアップして、技科大を盛り上げていきたいと思っています。


武藤浩行(むとう ひろゆき)/電気・電子情報工学系 准教授
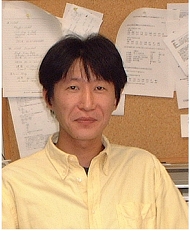 電気・電子情報工学系に准教授として着任しました。とは言うものの、豊橋の地は縁深く高専からの編入学を起点として、昨年度の高専教員人事交流で一年間久留米高専にお世話になった以外の約20年を豊橋で過ごしましたのでなんら違和感もなく4月からの新生活?を始めております。制度の都合で退職、新規採用となり「機械的に」新任教員となりましたので、これを機会に、新たな気持ちで教育・研究に邁進したく思っております。外から見る豊橋技科大は・・・・・指定の文字数に達してしまいましたので別の機会にさせていただきます。
電気・電子情報工学系に准教授として着任しました。とは言うものの、豊橋の地は縁深く高専からの編入学を起点として、昨年度の高専教員人事交流で一年間久留米高専にお世話になった以外の約20年を豊橋で過ごしましたのでなんら違和感もなく4月からの新生活?を始めております。制度の都合で退職、新規採用となり「機械的に」新任教員となりましたので、これを機会に、新たな気持ちで教育・研究に邁進したく思っております。外から見る豊橋技科大は・・・・・指定の文字数に達してしまいましたので別の機会にさせていただきます。


栗本宗明(くりもと むねあき)/電気・電子情報工学系 助教
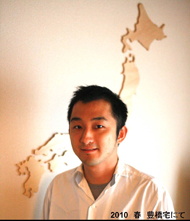 このたび電気・電子情報工学系の助教に着任いたしました。わたしは、ウィルスほどの大きさの極微小な粒子をプラスチックに複合した材料が、どのような電気抵抗を持つかを主に研究しています。これを用いた環境低負荷な電力機器の実現を目指しています。そして、材料を複合すると電気的特性はどうなるのかを明らかにしようとしています。2003年に名古屋大学で工学修士を取得、2007年までアイシン精機株式会社に所属、2010年に名古屋大学で工学博士を取得し、現在に至ります。研究と教育の両立を実現するよう仕事を進めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
このたび電気・電子情報工学系の助教に着任いたしました。わたしは、ウィルスほどの大きさの極微小な粒子をプラスチックに複合した材料が、どのような電気抵抗を持つかを主に研究しています。これを用いた環境低負荷な電力機器の実現を目指しています。そして、材料を複合すると電気的特性はどうなるのかを明らかにしようとしています。2003年に名古屋大学で工学修士を取得、2007年までアイシン精機株式会社に所属、2010年に名古屋大学で工学博士を取得し、現在に至ります。研究と教育の両立を実現するよう仕事を進めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。


関口寛人(せきぐち ひろと)/電気・電子情報工学系 助教
 平成22年4月1日付けで電気・電子情報工学系の助教に着任致しました。
平成22年4月1日付けで電気・電子情報工学系の助教に着任致しました。上智大学大学院理工学研究科電気電子工学専攻にて、半導体ナノ結晶を用いた発光デバイス応用に関する研究を行い、博士課程を修了しました。
研究では、半導体ナノテクノロジー技術を用いて、ナノ光源と呼ばれる非常に小さなサイズのLEDやレーザの開発を行いたいと考えています。もしこのような発光素子ができれば超高速な処理能力をもつコンピュータや高精細な網膜ディスプレイが実現できます。
教育・研究活動ともに、日々邁進していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。


田上英人(たのうえ ひでと)/電気・電子情報工学系 助教
 着任前は、本大学大学院博士課程の学生として、アークプラズマと薄膜形成に関する研究に従事していました。プラズマというと難しいと思われがちですが、身近なもので言うと太陽は自然界が生み出しているプラズマです。みなさんの生活の一部となっているプラズマを使って、役に立つものをつくる研究を行っています。今後は、本学の発展および地域に貢献できるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
着任前は、本大学大学院博士課程の学生として、アークプラズマと薄膜形成に関する研究に従事していました。プラズマというと難しいと思われがちですが、身近なもので言うと太陽は自然界が生み出しているプラズマです。みなさんの生活の一部となっているプラズマを使って、役に立つものをつくる研究を行っています。今後は、本学の発展および地域に貢献できるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。


平野雅嗣(ひらの まさつぐ)/情報・知能工学系 准教授
 平成22年度高専・両技科大学教員交流制度の派遣者(任期1年)として新居浜高専から異動してきました。こちらでは、昨年度に共同研究を行っておりました三浦研究室でお世話になっております。研究テーマとしては、新しいイメージング手法の開発と、医用画像処理に関する研究を行っております。技科大での教育・研究に触れ、高専へフィードバックしていきたいと思います。また、これまでと少し異なる研究分野に触れ、視野を広げていきたいと思います。宜しくお願い申し上げます。
平成22年度高専・両技科大学教員交流制度の派遣者(任期1年)として新居浜高専から異動してきました。こちらでは、昨年度に共同研究を行っておりました三浦研究室でお世話になっております。研究テーマとしては、新しいイメージング手法の開発と、医用画像処理に関する研究を行っております。技科大での教育・研究に触れ、高専へフィードバックしていきたいと思います。また、これまでと少し異なる研究分野に触れ、視野を広げていきたいと思います。宜しくお願い申し上げます。


大村 廉(おおむら れん)/情報・知能工学系 講師
 平成22年4月より情報・知能工学系(旧情報工学系)の講師に着任いたしました。センサを使って人の動きや状況を認識し、人の活動内容にあわせたサービスを行うコンピュータシステムの研究を行っています。現在は特に医療を対象としてこのような研究をおこなっており、看護師さんの業務支援やトレーニングができないか研究を行っています。理論的な研究に終わらず、本学の特徴である物を形にする技術を生かして、このようなシステムの実現を目指して行きたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
平成22年4月より情報・知能工学系(旧情報工学系)の講師に着任いたしました。センサを使って人の動きや状況を認識し、人の活動内容にあわせたサービスを行うコンピュータシステムの研究を行っています。現在は特に医療を対象としてこのような研究をおこなっており、看護師さんの業務支援やトレーニングができないか研究を行っています。理論的な研究に終わらず、本学の特徴である物を形にする技術を生かして、このようなシステムの実現を目指して行きたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。


増田幸宏(ますだ ゆきひろ)/建築・都市システム学系 准教授
 平成22年4月1日に本学の建築・都市システム学系に着任いたしました。私の専門である建築・都市環境工学は、人間を取り巻く環境空間の安全性、快適性、効率性、健康性を総合的に追求する学問です。豊橋技術科学大学の学生の皆さんと一緒に、社会の要請に応える新たな技術科学分野を力強く切り拓き、展開していきたいと考えております。また研究・教育活動を通じて、実践的な地域貢献活動を積極的に推進していきたいと考えております。これからどうぞよろしくお願いいたします
平成22年4月1日に本学の建築・都市システム学系に着任いたしました。私の専門である建築・都市環境工学は、人間を取り巻く環境空間の安全性、快適性、効率性、健康性を総合的に追求する学問です。豊橋技術科学大学の学生の皆さんと一緒に、社会の要請に応える新たな技術科学分野を力強く切り拓き、展開していきたいと考えております。また研究・教育活動を通じて、実践的な地域貢献活動を積極的に推進していきたいと考えております。これからどうぞよろしくお願いいたします


辻子裕二(つじこ ゆうじ)/建築・都市システム学系 准教授
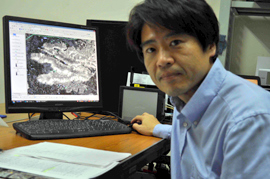 今年度、高専・両技科大教員交流制度により本学に赴任いたしました。豊橋での生活は6年程の経験があるのですが、様々な変化に日々戸惑っております。風の強さは変わっていないようですが...写真のように、研究面では遠隔(とくに宇宙)から「災害(とくに土砂災害)」や「環境(とくに森づくり)」をモニターする研究を進めています。コンピュータの中だけでなく、NPO活動等を通した防災や環境に関する意識啓発にも取り組んでいきたいと考えております。
今年度、高専・両技科大教員交流制度により本学に赴任いたしました。豊橋での生活は6年程の経験があるのですが、様々な変化に日々戸惑っております。風の強さは変わっていないようですが...写真のように、研究面では遠隔(とくに宇宙)から「災害(とくに土砂災害)」や「環境(とくに森づくり)」をモニターする研究を進めています。コンピュータの中だけでなく、NPO活動等を通した防災や環境に関する意識啓発にも取り組んでいきたいと考えております。


山本 綾(やまもと あや)/総合教育院 講師
 お茶の水女子大学大学院で言語学(英語学)を専攻し博士号を取得後、同大学研究員を経て平成22年4月1日付で総合教育院に着任しました。英語と日本語の談話標識(例えば “oh”や“well”、“じゃあ”や“だって”)に興味があり、これらを母語話者が会話でどのように用いているのか、子どもや非母語話者がどのように習得するのかなどの点について調べています。日々の授業と研究を通じ、本学で学ぶ皆さんの英語力増強を支援していきたいと考えています。どうぞよろしくお願いします。
お茶の水女子大学大学院で言語学(英語学)を専攻し博士号を取得後、同大学研究員を経て平成22年4月1日付で総合教育院に着任しました。英語と日本語の談話標識(例えば “oh”や“well”、“じゃあ”や“だって”)に興味があり、これらを母語話者が会話でどのように用いているのか、子どもや非母語話者がどのように習得するのかなどの点について調べています。日々の授業と研究を通じ、本学で学ぶ皆さんの英語力増強を支援していきたいと考えています。どうぞよろしくお願いします。


サンドゥー アダルシュ(SANDHU Adarsh)/エレクトロニクス先端融合研究センター 教授
 英国出身。2010年4月より豊橋技術科学大学エレクトロニクス先端融合研究センター教授。研究分野は、ナノスケールの走査型磁気顕微鏡、分子認識や医学へのナノバイオ磁気工学の応用などである。1985年、英国マンチェスター大学でPh.D取得。その後、東京大学生産技術研究所、(株)富士通研究所、ケンブリッジ大学キャヴェンディッシュ研究所、東京工業大学量子ナノエレクトロニクス研究センターで研究を続け、現在に至る。サイエンスライターとして科学技術の情報発信にも尽力。特例社団法人日本外国特派員協会(The Foreign Correspondents’Club of Japan)の正会員として選出され、2006年1月から「NPG Nature Nanotechnology」の編集顧問、2008年2月にはNature新雑誌「NPG Asia Materials」の編集長に就任。さらに、2010年2月に英国物理学会(IOP)のアジアパシフィック向けウェブサイト「IOP Asia Pacific」の設計を担当し、編集長に就任している。2010年3月からはサイエンスライターとして米国AAASサインス誌にも記事の提供を開始。スキー、ゴルフはもちろん、ハイキングなどは趣味の域を超える。さらに、昨年より小説を執筆。今年中の完成を目指し、ストーリーの展開に悩みながら楽しんでいる。日本での生活は25年。
英国出身。2010年4月より豊橋技術科学大学エレクトロニクス先端融合研究センター教授。研究分野は、ナノスケールの走査型磁気顕微鏡、分子認識や医学へのナノバイオ磁気工学の応用などである。1985年、英国マンチェスター大学でPh.D取得。その後、東京大学生産技術研究所、(株)富士通研究所、ケンブリッジ大学キャヴェンディッシュ研究所、東京工業大学量子ナノエレクトロニクス研究センターで研究を続け、現在に至る。サイエンスライターとして科学技術の情報発信にも尽力。特例社団法人日本外国特派員協会(The Foreign Correspondents’Club of Japan)の正会員として選出され、2006年1月から「NPG Nature Nanotechnology」の編集顧問、2008年2月にはNature新雑誌「NPG Asia Materials」の編集長に就任。さらに、2010年2月に英国物理学会(IOP)のアジアパシフィック向けウェブサイト「IOP Asia Pacific」の設計を担当し、編集長に就任している。2010年3月からはサイエンスライターとして米国AAASサインス誌にも記事の提供を開始。スキー、ゴルフはもちろん、ハイキングなどは趣味の域を超える。さらに、昨年より小説を執筆。今年中の完成を目指し、ストーリーの展開に悩みながら楽しんでいる。日本での生活は25年。


鯉田孝和(こいだ こうわ)/エレクトロニクス先端融合研究センター 特任准教授
 平成21年1月にテニュアトラック教員として採用された鯉田です。技科大に新しくできたこの研究センターで存分に研究ができる機会を与えて頂きました。
平成21年1月にテニュアトラック教員として採用された鯉田です。技科大に新しくできたこの研究センターで存分に研究ができる機会を与えて頂きました。私は脳科学研究をしています。興味を持っているのは視覚で、色や形を見て判断を行っているときの脳活動を、神経細胞一個一個のレベルで測定する実験をしています。研究室は建設中ですが、学部生や生徒の皆さんが研究室に配属するころには、実験が軌道に乗っているよう準備を進めています。


沼野利佳(ぬまの りか)/エレクトロニクス先端融合研究センター 特任准教授
 みなさま、はじめまして。この度、エレクトロニクス先端融合研究センターに参りました沼野利佳と申します。私は、修士まで工学部におりまして、その後、バイオをいたしてみようと、ゲノムと神経とバイオイメージングなどなどをのぞいてまいりました。どの分野でも、その筋のプロが切磋琢磨しており深遠な世界でした。そこで、新しいことを発見するには、やはり新しい実験系を模索しなければと思い、このたびのエレクトロニクス先端融合という新規性の高いプロジェクトに大変惹かれました。生物の本質に新しいアプローチで迫り、それを応用して人類、もとい、全生物のために役に立てたいというのが根幹にあります。概日リズムを外部から細胞レベルで制御することに挑戦する所存です。若輩者にて、いたらぬことが多いと思いますが、何卒、宜しくお願いいたします。
みなさま、はじめまして。この度、エレクトロニクス先端融合研究センターに参りました沼野利佳と申します。私は、修士まで工学部におりまして、その後、バイオをいたしてみようと、ゲノムと神経とバイオイメージングなどなどをのぞいてまいりました。どの分野でも、その筋のプロが切磋琢磨しており深遠な世界でした。そこで、新しいことを発見するには、やはり新しい実験系を模索しなければと思い、このたびのエレクトロニクス先端融合という新規性の高いプロジェクトに大変惹かれました。生物の本質に新しいアプローチで迫り、それを応用して人類、もとい、全生物のために役に立てたいというのが根幹にあります。概日リズムを外部から細胞レベルで制御することに挑戦する所存です。若輩者にて、いたらぬことが多いと思いますが、何卒、宜しくお願いいたします。


テイエテイエルコブ ズミトリー(Dzmitry Tsetserukou)/エレクトロニクス先端融合研究センター特任助教
 私は6年半前に、森と湖の国、ベラルーシから、山と海の国、日本に参りました。
私は6年半前に、森と湖の国、ベラルーシから、山と海の国、日本に参りました。2004年10月より文部科学省国費博士課程留学生として東京大学で学び、2007年に東京大学大学院 情報理工学系研究科 システム情報学専攻博士課程を修了しました。その後、東京大学で日本学術振興会(JSPS)の研究員を経て、今年から豊橋技術科学大学のエレクトロニクス先端融合研究センター特任助教に着任しました。
研究テーマは、着用型ロボット、力覚と触覚ディスプレイ、触覚コミュニケーション、バーチャルリアリティ、テレイグジスタンス、人間型ロボット、光学式トルクセンサです。
2010年First ACM Int. Conf. on Augmented Human, Best paper award, 2008年Int. Conf. on Instrumentation, Control and Information Technology (SICE), Finalist of Young Author’s Award and International Award, 2003年Conf. Young Scientists of the National Academy of Science of Belarus, Best paper award を受賞しました。IEEE(2005年〜),ACM(2010年〜)の会員です。
どうぞよろしくお願いいたします。
Self-introduction (English)
https://sites.google.com/site/dzmitrytsetserukou/


三澤宣雄(みさわ のぶお)/エレクトロニクス先端融合研究センター 特任助教
 4月1日付でエレクトロニクス先端融合研究センターに特任助教として着任致しました。昨年度末まで東京大学生産技術研究所で微細加工技術に基づいた電気機械システム、いわゆるMEMS(Micro Electro Mechanical Systems)と呼ばれる工学分野の研究に携わり、更に以前は岡崎市の分子科学研究所に所属しておりました。博士課程の学生時代から生体と人工的な系を融合させるような研究に漠然と興味を抱き、研究を進めて現在に至っております。技科大の誇る集積回路作製技術を礎にバイオロジーとMEMSを組み合わせた“BioMEMS”の道で頑張っていく覚悟です。
4月1日付でエレクトロニクス先端融合研究センターに特任助教として着任致しました。昨年度末まで東京大学生産技術研究所で微細加工技術に基づいた電気機械システム、いわゆるMEMS(Micro Electro Mechanical Systems)と呼ばれる工学分野の研究に携わり、更に以前は岡崎市の分子科学研究所に所属しておりました。博士課程の学生時代から生体と人工的な系を融合させるような研究に漠然と興味を抱き、研究を進めて現在に至っております。技科大の誇る集積回路作製技術を礎にバイオロジーとMEMSを組み合わせた“BioMEMS”の道で頑張っていく覚悟です。


ビールにまつわる話/環境・生命工学系 准教授 田中照通(たなか てるみち)
ビールはいつから飲まれていたのでしょう。文献によると紀元前5000年前にはシュメール人によって小麦と大麦が栽培されていたとあります。紀元前4000年前には同じくシュメール人によってビールが飲まれていたようです。また紀元前3300年前にはエジプトでもビールが飲まれていたという記録があります。
ビールの成立とパンの成立には深い関わりがあるようです。古代のビールは「液体のパン」といった感じです。栽培された麦をそのまま食べてもヒトはデンプンを消化することができません。ヒトはαアミラーゼしか持っていないので、麦のデンプンを消化するためにはデンプンを加熱によってα化しておくことが必要です。お米を炊くのもパンを焼くのもこのためです。古代の人たちはパン作りにある工夫を凝らしました。麦を水に浸してしばらくおき、発芽させて麦芽にしてからパンを作ったのです。麦は種子ですから、水に浸すと発芽します。すると自らのデンプンを分解して成長のエネルギー源となるグルコース(ブドウ糖)を作ります。麦芽から作るパンは甘く旨味が増します。このパンを砕いて水を加えて空気中の酵母によって自然発酵したものが最初のビールと言われています。最初のビールは今のような透き通ったものではなく、甘みと栄養が詰まったどぶろくや白酒(甘酒)のような飲み物であったようです。麦芽を使ったのは、偶発的な事故であったと想像されています。倉庫に保存していた麦に雨水がかかり、いつの間にか麦芽になってしまったというのが真相でしょう。もったいないので使ってみたら、ことのほか美味であったということでしょうか。
エジプトの時代になると酵母による発酵過程がパン作りの段階にも応用されるようになったようです。麦芽でパンを作った後に、発酵によって十分にパンが膨らむ過程を取り入れ、その後に焼いてからビール作りに用いたようです。
このような麦の食べ方は今日にもつながっています。オートミールという麦の粥がそれにあたります。日本人にはあまり評判がよくない食べ物の一つですが、こんな過去をもっています。
ご存じのようにビール酵母とパン酵母は同じものです。一見異なる食品になぜ同じ酵母が使われているのかおわかりになりましたか?パンの発酵過程で臭いを嗅いでみるとほんのりとアルコールの香りがするのがわかるでしょう。
どこかのビール会社の宣伝でいうようにビールはみな大麦から作られているものと思ったらいけません。うどんやパンと同じ小麦から作られているビールだってあります。色が薄くて甘みのあるヴァイツェン(Weizen)は小麦から作られるビールです。地ビール工房でヴァイツェンが美味しければ、そのビール工房は当たりです。
最近訪れた地ビール工房では「小樽麦酒」が最高でした。ビールだけでなく料理も印象値を上げています。よく行く近場の浜松の「マインシュロス」も最近旨さを増しました。価格で印象値を上げているのは横浜の「うまやの食卓」です。ランチならコーヒーよりもビールがお手頃なのは嬉しいです。
(天伯No.126にも地ビール工房の関連記事を掲載しています)
近頃の不況の影響からか営業を止めてしまう地ビール工房も多い中、お気に入りのビール工房には生き残って欲しいですね。
ビールの成立とパンの成立には深い関わりがあるようです。古代のビールは「液体のパン」といった感じです。栽培された麦をそのまま食べてもヒトはデンプンを消化することができません。ヒトはαアミラーゼしか持っていないので、麦のデンプンを消化するためにはデンプンを加熱によってα化しておくことが必要です。お米を炊くのもパンを焼くのもこのためです。古代の人たちはパン作りにある工夫を凝らしました。麦を水に浸してしばらくおき、発芽させて麦芽にしてからパンを作ったのです。麦は種子ですから、水に浸すと発芽します。すると自らのデンプンを分解して成長のエネルギー源となるグルコース(ブドウ糖)を作ります。麦芽から作るパンは甘く旨味が増します。このパンを砕いて水を加えて空気中の酵母によって自然発酵したものが最初のビールと言われています。最初のビールは今のような透き通ったものではなく、甘みと栄養が詰まったどぶろくや白酒(甘酒)のような飲み物であったようです。麦芽を使ったのは、偶発的な事故であったと想像されています。倉庫に保存していた麦に雨水がかかり、いつの間にか麦芽になってしまったというのが真相でしょう。もったいないので使ってみたら、ことのほか美味であったということでしょうか。
エジプトの時代になると酵母による発酵過程がパン作りの段階にも応用されるようになったようです。麦芽でパンを作った後に、発酵によって十分にパンが膨らむ過程を取り入れ、その後に焼いてからビール作りに用いたようです。
このような麦の食べ方は今日にもつながっています。オートミールという麦の粥がそれにあたります。日本人にはあまり評判がよくない食べ物の一つですが、こんな過去をもっています。
ご存じのようにビール酵母とパン酵母は同じものです。一見異なる食品になぜ同じ酵母が使われているのかおわかりになりましたか?パンの発酵過程で臭いを嗅いでみるとほんのりとアルコールの香りがするのがわかるでしょう。
どこかのビール会社の宣伝でいうようにビールはみな大麦から作られているものと思ったらいけません。うどんやパンと同じ小麦から作られているビールだってあります。色が薄くて甘みのあるヴァイツェン(Weizen)は小麦から作られるビールです。地ビール工房でヴァイツェンが美味しければ、そのビール工房は当たりです。
最近訪れた地ビール工房では「小樽麦酒」が最高でした。ビールだけでなく料理も印象値を上げています。よく行く近場の浜松の「マインシュロス」も最近旨さを増しました。価格で印象値を上げているのは横浜の「うまやの食卓」です。ランチならコーヒーよりもビールがお手頃なのは嬉しいです。
(天伯No.126にも地ビール工房の関連記事を掲載しています)
近頃の不況の影響からか営業を止めてしまう地ビール工房も多い中、お気に入りのビール工房には生き残って欲しいですね。