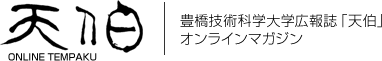もくじ
クリックすると各記事の先頭に移動できます
クリックすると各記事の先頭に移動できます

ABUロボコンに向けて(NHK大学ロボコン2009で優勝、2連覇達成)/ロボコン同好会顧問 機械システム工学系教授 鈴木新一(すずき しんいち)
 去る6月7日に、NHK大学ロボットコンテスト2009が開かれ、本学のロボコン同好会は、昨年に引続き優勝しました。2連覇です。過去16回の大会中、今回が6度目の優勝であり、2連覇は、1994、95年以来、2度目です。準優勝は金沢工業大学であり、本学と金沢工業大学が、8月20日から開かれるABUアジア太平洋ロボットコンテスト(ABUロボコン)に出場します。
去る6月7日に、NHK大学ロボットコンテスト2009が開かれ、本学のロボコン同好会は、昨年に引続き優勝しました。2連覇です。過去16回の大会中、今回が6度目の優勝であり、2連覇は、1994、95年以来、2度目です。準優勝は金沢工業大学であり、本学と金沢工業大学が、8月20日から開かれるABUアジア太平洋ロボットコンテスト(ABUロボコン)に出場します。昨年のABUロボコンはインドのプネで開かれました。本学のロボコンチームは日本代表としてそれに出場し、3位入賞を果たしました。今年のABUロボコンは東京で開かれます。2002年の第1回大会以来、2度目の日本開催です。そして、本学は3度目のABUロボコン出場です。
ロボットコンテストのルールは毎年変わります。昨年までのロボコンでは、2つのチームが、競技場で箱を取り合ったり、ゴールにボールを入れあったりしていました。それらは、サッカーやラグビーの試合と似ています。試合開始直後に、高速走行の自動ロボット同士が互いにぶつかり合い、相手の動きを封じようとします。そこでは、ロボットの性能はもちろんですが、勝つための戦略が重要な位置を占めています。
しかし、今年のロボコンはちょっと違います。不安定な駕籠に小型のロボットを乗せ、それを別の2台のロボットで運びます。江戸時代の駕籠と同じです。運ぶコースの途中には、「山」や「林」などの障害物が待っています。対戦するチームのロボットが、コース上で互いに接触することはありません。これは、サッカーやラグビーと言うよりも、陸上競技の障害物レースに似ています。そのため、対戦相手を研究し、勝つための戦略を作るというようなことは、あまり重要ではありません。それよりも、与えられたコースを、滑らかに、正確に、そしてどれだけ速く動けるかが問題となります。そのため、ロボットの設計製作技術そのものが問われます。これは技術科学大学を名乗る本学にとって、是非とも勝ちたい試合です。
2002年の第1回ABUロボコンの時も、豊橋技科大と金沢工業大学が、日本代表として出場しました。その時は両大学とも準決勝で破れ、3位に甘んじました。優勝はベトナムであり、準優勝は中国でした。これは、あまり思い出したくない記憶です。
前述のように、今年のテーマは、豊橋技科大にとって挑戦しがいのあるものです。したがって今年のABUロボコンでは、是非とも決勝戦に進めることを願っています。ベトナムや中国は今年も強いとの噂を聞いていますが、出来ることならば、金沢工業大学と決勝戦を戦ってみたいと思います。


キャンパス内を探険!〜豊橋技術科学大学の新しい建物たち〜/総務課広報係長 丸山憲洋(まるやま のりひろ)
 みなさん、こんにちは!
みなさん、こんにちは!今日は豊橋技術科学大学で新しくできた建物を紹介したいと思います。
昨年度から榊学長の下、キャンパスマスタープランに基づいていくつかの建物等ができましたので、ご紹介します。
では、出発します!
まず、事務局棟とA棟(講義棟)をつなぐ渡り廊下です。
これで雨が降っても、傘を差さずに移動できるようになりました。

見てください、こんなに広いです!
あっ!こんな所にベランダが?洗濯物でも干すのかな?
※ 撮影のために特別に開けてみました
ここにも扉がありますね、行ってみましょう。
ぎょぇーーーーこれは危険だ!!
 |
| ※ 普段は施錠されているため安全です |
落ちなくて良かったなぁ、さぁ気を取り直して次に行きましょう。

 いたたっ!(写真)天井を見上げていたら、柱にぶつかってしまった。
いたたっ!(写真)天井を見上げていたら、柱にぶつかってしまった。こんな所に、大きな屋根(テント)ができました!
この屋根のおかげで、雨の心配は無くなりましたね!しかも夏は日陰に!
これからの季節は大活躍ですね。
ここは心地よい憩いの場所になりそうです。
もっとベンチがあるとなお良いかもしれませんね。

次は、どんな新しいものに出会うかな?
おや?こんな所に看板が・・・
「Sakaki Park」・・・サカキパーク??
奥の方まで道が続いていますね、公園みたいですね。

少し歩いてみましょう!
おや?こんな所にベンチとテーブルが?
疲れたので座ってみましょう! ふたが付いていますね、取ってみよう。
ここで、バーベキューができるのか!(学内者のみ利用可能です)
 |  |
| テーブル発見! | ここにバーベキュー用器具をセットできます! |

そうそう、それぞれの建物にペイントがなされているんですよ。
個々の建物が何棟かがすぐ分かるように色をそれそれ付けました!
上の方には、その棟の頭文字があります。
では、噂の新学生宿舎に行ってみましょう。
おーーー大きな建物ですね、セキュリティーも完璧です!
部屋の中を見てみましょう!
机もベッドもエアコンも付いてますね、お風呂とトイレは別々に分かれています。
完全にプライバシーが守られています。
 |  |
 |  |

宿舎のベランダからの眺めもなかなかですね。
ここからなら、研究室も近いから学生の皆さんは住んでみたく
なるのでは?
広いキャンパスの中を歩き回ったので少し疲れてしまいました・・・今回のレポートはこれで終わりたいと思います。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。