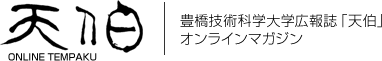クリックすると各記事の先頭に移動できます

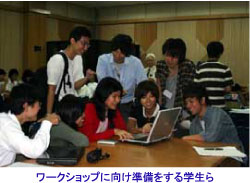 際的に活躍できる人材の育成のため外国の大学等との連携・交流の機会を提供する「大学生国際交流プログラム」を工学教育国際協力研究センターの協力により実施しました。5回目となる今年は、平成19年11月26日(月)〜11月30日(金)、インドネシアのバンドン工科大学を会場に、本学学生14名とバンドン工科大学学生15名、ガジャマダ大学学生4名そしてベトナムのホーチミン市工科大学学生4名が参加し、「地球温暖化とエンジニアの役割」をテーマとした講義と学生主体のワークショップを開催しました。
際的に活躍できる人材の育成のため外国の大学等との連携・交流の機会を提供する「大学生国際交流プログラム」を工学教育国際協力研究センターの協力により実施しました。5回目となる今年は、平成19年11月26日(月)〜11月30日(金)、インドネシアのバンドン工科大学を会場に、本学学生14名とバンドン工科大学学生15名、ガジャマダ大学学生4名そしてベトナムのホーチミン市工科大学学生4名が参加し、「地球温暖化とエンジニアの役割」をテーマとした講義と学生主体のワークショップを開催しました。ワークショップでは、日本・インドネシア・ベトナムそれぞれの算数・数学教育について発表を行い、異文化に対する理解を深めた後、異常気象、自然
 災害の多発、海水面上昇など、世界各地で発生する地球温暖化により引き起こされる問題に対し、工学系の知識を持つエンジニアとして何をすべきかについてグループに分かれ討論、その後各グループによる発表を行い、活発な意見交換が交わされました。本学学生は普段使用する機会のない英語で議論を行いましたが、文化・習慣の違いがあるにも関わらず、お互いの意見を尊重しあい、防災や日本の国際協力についても理解を深めるとともに、インドネシア・ベトナムの学生との友好を深めることができました。
災害の多発、海水面上昇など、世界各地で発生する地球温暖化により引き起こされる問題に対し、工学系の知識を持つエンジニアとして何をすべきかについてグループに分かれ討論、その後各グループによる発表を行い、活発な意見交換が交わされました。本学学生は普段使用する機会のない英語で議論を行いましたが、文化・習慣の違いがあるにも関わらず、お互いの意見を尊重しあい、防災や日本の国際協力についても理解を深めるとともに、インドネシア・ベトナムの学生との友好を深めることができました。3日間のワークショップの後、本学学生およびベトナムの学生は、独立行政法人国際協力機構(JICA)のプロジェクト「生物多様性保全センター」を訪問、プロジェクト担当員より話を聞くなど、インドネシアにおける開発や国際協力についても、理解を深めました。


高専訪問エキスパートとして、北陸地区(福井・富山・石川)の高専を訪問しています。併せて、本学の教育研究活性化経費(高専連携)に基づく共同研究の打ち合わせにかこつけて、鈴鹿高専や木更津高専でも本学のPRをさせていただいています。各高専の先生方には多忙を極めておられるにもかかわらず嫌な顔一つせずに大学説明会や意見交換会を開催していただき、大変ありがたく存じております。そんななかで強く感じるのは、高専の先生方の「学生たちのためならば」という姿勢です。常に学生を思って自己犠牲の精神で学習・生活・進路などの指導にあたっておられる様子が、意見交換会でのご発言などからもひしひしと伝わってきて、まさに頭の下がる思いです。
省みて大学側はどうでしょう。学生を受け入れるときだけ調子の良いことを言って、後から高専の先生方をガッカリさせるような結果になっていないでしょうか。複数の大学の合同説明会に出席することもあります。なかにはTVショッピングさながらの説明で学生を惹きつける大学もあります。その後のことについては知る由もありませんが、高専の先生方の冷ややかな目が何かを語っているようにも感ぜられます。せめて本学は、たとえ地味でも「あの大学なら大丈夫」と高専の先生方が安心して卒業生を託して下さるような大学でありたい(あり続けたい)と願いつつ、実直な大学PRを心がけています。
(機械システム工学系 准教授 鈴木孝司(すずき たかし))


サイエンスカフェ、フェルマーの定理、理科ぎらい
 |
語らいにでてきた言葉でつないだしりとりです。サイエンスカフェは、科学者と一般市民が、コーヒーやお茶を飲みながら、サイエンスについてフランクに語り合うものです。本稿執筆時までに6回のサイエンスカフェを行ない、あわせて117名の市民の方々の参加をいただいています。
ゲストスピーカーは高校教員
大学がこうしたサイエンスカフェを行なう場合、所属する大学教員がゲストスピーカー役になるのが普通です。しかし、本サイエンスカフェでは、地域の高校教員をゲストスピーカーにまねいています。高校教員は、本来、各専門分野の科学者です。例えば、数学の先生は数学者であり、化学の先生は化学者です。この先生方の専門性をいかしたのが、本サイエンスカフェです。表のように、いずれのテーマを見ましても、とても興味深く、専門性の高い話題がとりあげられています。
|
大学は場を提供
すべての市民がサイエンスについての基本的な素養、科学リテラシーを身につけることが求められています。とりわけ、科学技術の進展は著しく、継続的に学びつづけることが必要です。本サイエンスカフェは、こうした地域のニーズに対する本学のひとつの回答と考えています。
会場は、本学のサテライトオフィスです。豊橋駅から徒歩5分です。市民のみなさんに気軽にお越しいただける場所です。参加受付業務や会場設営など運営は、地域連携係が行なっています。司会は、筆者がつとめさせていただいております。運営に要する経費の多くは、財団助成等の外部資金です。
理科はキライだったのですが
「高校生の頃は、理科、特に物理は大嫌いでした。でも、今日のお話しのような授業だったら、違っていたかなぁ。」「数学が苦手だという人もいらっしゃるなかで、こうした議論ができることがすごく楽しい。」こうした参加者、ゲストスピーカーの声にこたえられるサイエンスカフェを続けていきたいと思います。
(東三河サイエンスカフェ実行委員会代表 知識情報工学系 准教授 河合和久(かわい かずひさ))