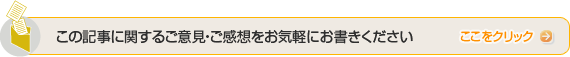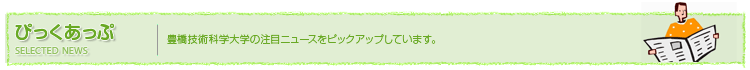
もくじ
クリックすると各記事の先頭に移動できます
クリックすると各記事の先頭に移動できます

文部科学大臣表彰若手科学者賞を受賞したインテリジェントセンシングシステムリサーチセンターの高尾英邦(たかお ひでくに)准教授にインタビュー
文部科学大臣表彰若手科学者賞(受賞テーマは「半導体 工学分野における機能化センシングデバイスの研究」)を受賞されたインテリジェントセンシングシステムリサーチセンターの高尾英邦准教授にうかがいました。
工学分野における機能化センシングデバイスの研究」)を受賞されたインテリジェントセンシングシステムリサーチセンターの高尾英邦准教授にうかがいました。
 工学分野における機能化センシングデバイスの研究」)を受賞されたインテリジェントセンシングシステムリサーチセンターの高尾英邦准教授にうかがいました。
工学分野における機能化センシングデバイスの研究」)を受賞されたインテリジェントセンシングシステムリサーチセンターの高尾英邦准教授にうかがいました。高:高尾英邦准教授
広:広報室員(古川・本間)
広:本日はお忙しい中、ありがとうございます。文部科学大臣表彰若手科学者賞の受賞大変おめでとうございます。昨日表彰式でしたが、賞を受賞されて、今のお気持ちを一言お願いします。
高:受賞できたこと自体、実感がありませんでした。評価されたことはたいへんうれしく思っています。
広:この受賞につながった研究活動について、教えてくださ
 い。
い。高:学生の頃から10年以上続けてきたMEMS分野の研究です。半導体を使って集積回路、つまりLSIと、微小機械構造のセンサを一体化する技術の研究で、自身のアイデアを形にして、今までにない新しいセンサを創ることを追及してきました。ただ、この研究は一人では実施できません。共同で、教員、学生および多くの方の協力があって、出来上がるのです。
広:ところで昨日の表彰式はどんな様子でしたか。
高:時間は12時開始の50分間でした。雰囲気は卒業式のようでした。
式の流れは、まず全員で国歌斉唱しました。順番で賞ごとに名前が呼ばれ、席で立ちます。受賞者を代表して、京都大学の山中先生が2分くらいの短いあいさつしました。途中で渡海文部科
学大臣は退席されましたね。会場の写真がありますが見ますか。

学大臣は退席されましたね。会場の写真がありますが見ますか。
広:会場いっぱいずらりと人が並んでいますね。また井上先生とご一緒に記念撮影をされていますね。
高:私の席からですと、隙間からしか渡海文部科学大臣を撮影出来なかったですね。(笑)
広:ところで、高尾先生のご出身はどちらですか?
高:香川県高松市です。
広:先生は本学の卒業生でありますが、高専からの編入学ですね、どちら高専ですか。
高:高松高専です。電気工学科です。
広:なぜ高専へ進学を決めたのですか。
高:当時から工学系の技術に関する興味がとても強く、すぐに実学に触れたかったからですね。
広:電気工学科を選ばれたのはなにか理由があったのですか?
高:電気と機械で迷いましたよ。でも電気への興味が強かったからですね。今は電気と機械の両方に携わる仕事をしています。
広:技科大(本学)への進学は迷わず決めたのですか?
高:高専の時に、特に大学進学を決めていたわけではありません。私は、その時その時で進路を決めてきました。たまたまその方向に結果がでたということで、もっと勉強したいという気持ちがあったからでしょう。大学院の修士課程にも当初は進学を考えていなかったくらいです。しかしもっと研究をしたいという気持ちになったから、進学を決めました。博士課程への進学も同じ理由です。
広:意外な感じに思えますね。
高:周りに勧められたこともありますが、でもまず研究することが好きなんですよ。興味があって、好きなことならどんなに大変なことでも続けられますよね。
広:今後、先生に続く、研究者を目指す方や学生の方へ一言いただけないでしょうか。
高:これから研究者を目指す方や学生の方へは、好きこそものの上手なれと言いますが、興味があり、好きなテーマを見つけてほしいですね。どういう仕事がしたいかということは、手段の選択にすぎません。好きなことを突き詰めてほしいです。ただ大学では、次の学問につながる様な結果を出すことも重要なことだと思っています。ここはそのようなところですからね。

広:大変貴重なお話し、ありがとうございました。
取材を終えて:とにかく作ること(研究すること)を追及することが好きという姿勢に、ものづくりの原点がここにあると思いました。印象的なことは、実学に触れることが好きで、早く実学を勉強したかったから高専に進んだと。さらにその延長線上に技科大があり、技科大での研究が続いていることに、本学の存在そのもののような先生に感動しました。お話をうかがいながら、好きなことを見つけることでどんなに世界が広がっていくかをつくづく感じました。
好きなことを見失っている方、本学で探してみませんか。
(ただし工学(技術)が好きなことが条件です。)
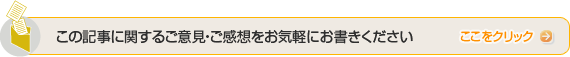

超伝導科学技術賞を受賞したエコロジー工学系の田中三郎(たなか さぶろう)教授にインタビュー
 社団法人未踏科学技術協会超伝導科学技術研究会第12回超伝導科学技術賞(受賞テーマ:高温超伝導SQUIDを用いた食品内金属異物検査装置の開発」)を受賞されたエコロジー工学系の田中三郎教授にうかがいました。
社団法人未踏科学技術協会超伝導科学技術研究会第12回超伝導科学技術賞(受賞テーマ:高温超伝導SQUIDを用いた食品内金属異物検査装置の開発」)を受賞されたエコロジー工学系の田中三郎教授にうかがいました。田:田中三郎教授
広:広報室員(本間)
広:本日はお忙しい中、ありがとうございます。また受賞おめでとうございました。今までにもたくさんの賞を受賞されていますが、今のお気持ちをお聞かせください。
田:この賞はいろいろな超伝導を使ったパワー応用というのはたくさんあるのですが、私どもの行ったエレクトロニクス応用というのはほかに実用化したものはなかった。この異物検査装置は世界でもどこもやっていない、日本でも初めて実用化されたものです。この技科大が中心で、この小さな大学で開発して、世の中に実用化されて出たということはうれしいことですね。開発の試みをしているところはあるのですが、実用化されて市販されたのは初めてなのです。この賞は実用化されたことを評価する賞なのです。そういう意味では大変うれしいですね。これまでは食品を対象に異物検査をしていたのですが、これからは対象を変えて、リチウムイオンバッテリーの安全性に対して応用できそうです。ただ、センサもそのままでは使えないので、改良していかなければいけないのですが、社会全体の役に立つことですから進めていかなければいけないと考えています。
広:新聞記者でしたら、何年後くらいにと聞くところですが、どうでしょうか。
田:たぶん実証は2年後くらいを考えています。
広:先生は本学の卒業生ですが、どちらの高専出身ですか。
田:大阪府立高専出身です。生まれは兵庫県伊丹です。
広:高専進学を選ばれたのは、どうしてですか。
田:生まれ持って機械いじりや電気いじりが大変好きだったんですね。
ものごころついたときから好きだったんですね。とにかく早く実学に触れたかったからですね。
広:電気を選ばれたのはどうしてですか。
田:それはなぜかわからないですね。それは電気に興味があったのと、電気はユニバーサルで、何でも幅広い。
でもそんなこと考えて決めたわけではない。電気が好きだった。
広:技科大への進学を決めた理由は?
田:もっと深くやりたい。そのころ受け入れてくれる大学は少なかったから豊橋を選んだのです。
広:学生時代はどんな学生でしたか。
田:結構、英語が好きでした。実験もすごく好きでした。当時は知り合いの新聞屋さんが安価で英字新聞を入れてくれていました。学生のころ作製したトランジスタ式の高電圧発生装置がまだ、水野彰教授の研究室に残されていたことには驚きました。いい物を作っておくと壊されずに残るのです!
広:先生は寮生活でしたか?

田:下宿でした。柳生橋の付近の間貸しの部屋にいました。4000円くらいでしたね。今では考えられない。駅まで近かったからよく飲みにも行きました。
広:企業経験後、戻った時の技科大はどうでしたか。
田:違和感はなかったですよ。思ったことはここの学生は工学のことはいろいろ知識があるのですが、英語が全然できない。(笑)英語は好きにならないとできるようにならないですね。興味があれば伸びるんですよ。
広:話が戻りますが、この研究に費やした年月はどのくらいですか。

田:2000年から進めてきました。8年ですね。実用化したのはもう少し前ですが。文科省の都市エリア事業で3年+3年の6年です。
広:研究費はどのくらい使われたのでしょうか。
田:人件費を入れないで5000万円くらいかな。共同研究先のアドバンスフードテックでは1億円以上使っているでしょう。
広:今後の若手の方、学生の方へ一言いただけますか。
田:エンジニアリング、技術に対して、その開発にあたっては振り返って、どういった原理原則に基づいて動いているか、ということを考えてほしいですね。まずは、工学を好きになってほしいですね。さらにはモノの意味について考えてほしい。とにかく自分の好きなことに興味を持つことが大事でしょう。ものを作るというのは自分でひとつひとつ考えて設計していくことが大事ですから。何もないところから作る楽しさを知ってほしいですね。私の研究室では計測器は購入しますが、実験装置など全部作っていますよ。電気、機械、化学の知識がないとできません。また、興味があって、好きでないと長続きしません。それでないと知識は増えていかないですからね。
広:本日は貴重な時間、ありがとうございました。
取材を終えて:この後、向い側にある研究室を見学させていただきました。4年生の学生さんが実験していました。研究室で材料を削る(加工)ところから、作ったモノや機器を見せていただき、町工場のような部屋でした。研究室に配属された学生はまず”はんだごて”が使えるように実習するとのこと。モノづくりの原点がここにもありました。その隣の部屋には、食品内金属異物検査装置のモデル装置が置いてありました。
ここでも好きであることがキーワードでした。
今後の取材でどれだけ多くの「好き」を見つけられるでしょうか。
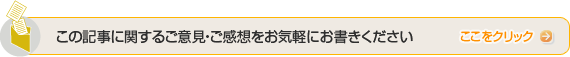

エンテベの動物園(ウガンダ研修レポートVol.2)/生産システム工学系学部4年 春名 将資(はるな まさし)
春名さんは、平成20年4月から平成21年3月上旬までの1年間、アフリカ・ウガンダ共和国でエイズ遺児約200万人のためのエイズ遺児家庭訪問調査や「あしながウガンダレインボーハウス」での心のケア活動を行っています。そんな春名さんからの現地レポートをご紹介します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 時が経つのは早いもので、ウガンダに来てもう二ヶ月が過ぎようとしている。少しずつこちらの生活にも慣れ、ウガンダライフを楽しめるようになってきた今日この頃だ。今月は子供たちにとって楽しみでたまらないイベント「アウティング(遠足)」があり、たくさんの子供たちを連れてエンテベの動物園へ行った。今回はその事を書こうと思う。
時が経つのは早いもので、ウガンダに来てもう二ヶ月が過ぎようとしている。少しずつこちらの生活にも慣れ、ウガンダライフを楽しめるようになってきた今日この頃だ。今月は子供たちにとって楽しみでたまらないイベント「アウティング(遠足)」があり、たくさんの子供たちを連れてエンテベの動物園へ行った。今回はその事を書こうと思う。
当日の朝集合場所に行き、子供たちを待っていると、続々と子供たちがやってきた。しかし、何かいつもと雰囲気が違う気がした。確かに何かが違う。でも、これと言って浮かんでこなかった。すると、一人の男の子が来て私はハッとした。「おぉ!」思わず声を上げた。彼はどこかの国の王子様っぽい、「これぞ我が家のザ正装!」と言わんばかりの洋服を身にまといやって来たのである。なんとも言えない愛くるしさだ。思わず写真を撮ってしまった私である。そう、見渡すと子供たちはみんないつもより格段に綺麗な服でやって来ていたのである。中には「えっ?ディズニーのパレードから来たんですか?!」と聞きたくなるようなドレスを着た女の子もいた。子供たちのこの日に寄せる思いは相当だ。彼らを見るとこの遠足をどれほど楽しみにしていたのか言われなくてもビシバシ伝わってきた。彼らの日常の中では、こんな非日常的な楽しみは望んでも得られるはずも無く、毎日毎日同じような生活を強いられている。彼らの家には余暇を楽しむほどのお金は無い。日々の生活をしていくだけで精一杯だ。だからこそ私はこのアウティングを少しでも楽しいものにして、子供たちの笑顔の花をたくさん咲かせてやろうと、あいつらの一生の思い出に残る最高の日にしてやろうと、心から思った。
 動物園に着き、子供たちが動物を見て回っている間、私はチェックポイントである「オーストリッチ」と言うダチョウに似たでかい鳥の所で子供たちが来るのを待っていた。聞くと、やたらと広い(おそらく野球場くらいある)敷地の中にたった5頭しかいないらしい。日本の動物園事情を考えるとここだけで一つの動物園が出来そうである。・・・どう考えても無駄に広い。そう思うのは私が日本人だからだろうか?いや、おそらく違う。なぜならどこにもオーストリッチがいないからだ。そこにはただ豊かな自然が広がっていた。「わぁ、すごい!さすがウガンダ!やっぱり自然が豊かやなぁ〜。・・・違う違う。」国立公園ならまだ分かるが、ここは動物園だ。子供たちが動物を見るためにわくわく胸を弾ませやって来る。それなのに何もいないのである。子供たちはいったい何を見ればいいのだろうか?ウガンダの自然?そんなの子供らは毎日見ている。私はあせった。いっそのこと私が柵の中に入ってオーストリッチ風に現れようかとも思った。しかしそれはまずい・・・それではオーストリッチではなく「ヒト」だ。まぁ彼らにとって日本人も珍しいからいいかなぁ・・・?いや全然ダメだ。焦っているちょうどその時に、私に神が舞い降りた。私は日本人なら誰でも知っているであろう、ムツゴロウさんを思い出したのだ。彼は言っていた、「動物と仲良くなりたければ動物になれ。」と。つまり「オーストリッチと仲良くなりたければオーストリッチになれ。」という事だろう。私に考える暇など無かった。いつ子供たちが来てもおかしくない。しかし、彼らの笑顔が曇るのだけはどうしても見たくない。私に迷いは無かった。オーストリッチの鳴き声など知らないが(そもそも鳴くのか?)私の知っている限りの鳥風の鳴き声を連発した。幸いそこには警備員の方しかいなかったので、私に失うものは何も無かった。それを見て警備員の方は爆笑していたのだが・・・。しかし一向に鳥は現れない。気配すらない。少し経ち、私は鳴きつかれやめてしまった。何となく鳥の鳴く気持ちが分かった気がする。「ありがとうムツゴロウさん。僕は精一杯やったよ。でも僕には無理だったよ、オーストリッチ・・・。」少し落ち込んだが、くよくよしても仕方ないと思い、私は子供たちに内緒で、披露する準備をしていたウガンダの歌の練習を始めた。すると、遠くに米粒のように小さく見える鳥が現れた。何と何とそれがオーストリッチだったのだ。私のテンションは一気にアップした。これでもかと言わんばかりに歌を熱唱した。その歌に釣られたのか、面白いように二頭のオーストリッチが私の方へ集まってきた。そして、ついには数頭が私の柵の目の前までやって来たのである。近くで見る彼らは2メーターを優に越えていた。ヤツの前足で蹴られたら私の命はないだろう。それくらいとてつもなく迫力があった。少ししてから、子供たちが続々とやってきた。その鳥を発見するや否や子供たちは一斉に駆け寄り、目を飛び出そうなくらい見開いて、まじまじとその巨大鳥を見ていた。ほんとに良かった。私にとってその鳥を見るよりも彼らの笑顔を見る方が何よりうれしかった。なぜ鳥が集まってきたのか、理由は私には分からない。私の思いが伝わったのか、それとも偶然なのか・・・どちらにせよ歌の練習もできたし、子供たちに鳥も見せることも出来たから結果オーライだ。これこそ本当の「一石二鳥」なのか?
動物園に着き、子供たちが動物を見て回っている間、私はチェックポイントである「オーストリッチ」と言うダチョウに似たでかい鳥の所で子供たちが来るのを待っていた。聞くと、やたらと広い(おそらく野球場くらいある)敷地の中にたった5頭しかいないらしい。日本の動物園事情を考えるとここだけで一つの動物園が出来そうである。・・・どう考えても無駄に広い。そう思うのは私が日本人だからだろうか?いや、おそらく違う。なぜならどこにもオーストリッチがいないからだ。そこにはただ豊かな自然が広がっていた。「わぁ、すごい!さすがウガンダ!やっぱり自然が豊かやなぁ〜。・・・違う違う。」国立公園ならまだ分かるが、ここは動物園だ。子供たちが動物を見るためにわくわく胸を弾ませやって来る。それなのに何もいないのである。子供たちはいったい何を見ればいいのだろうか?ウガンダの自然?そんなの子供らは毎日見ている。私はあせった。いっそのこと私が柵の中に入ってオーストリッチ風に現れようかとも思った。しかしそれはまずい・・・それではオーストリッチではなく「ヒト」だ。まぁ彼らにとって日本人も珍しいからいいかなぁ・・・?いや全然ダメだ。焦っているちょうどその時に、私に神が舞い降りた。私は日本人なら誰でも知っているであろう、ムツゴロウさんを思い出したのだ。彼は言っていた、「動物と仲良くなりたければ動物になれ。」と。つまり「オーストリッチと仲良くなりたければオーストリッチになれ。」という事だろう。私に考える暇など無かった。いつ子供たちが来てもおかしくない。しかし、彼らの笑顔が曇るのだけはどうしても見たくない。私に迷いは無かった。オーストリッチの鳴き声など知らないが(そもそも鳴くのか?)私の知っている限りの鳥風の鳴き声を連発した。幸いそこには警備員の方しかいなかったので、私に失うものは何も無かった。それを見て警備員の方は爆笑していたのだが・・・。しかし一向に鳥は現れない。気配すらない。少し経ち、私は鳴きつかれやめてしまった。何となく鳥の鳴く気持ちが分かった気がする。「ありがとうムツゴロウさん。僕は精一杯やったよ。でも僕には無理だったよ、オーストリッチ・・・。」少し落ち込んだが、くよくよしても仕方ないと思い、私は子供たちに内緒で、披露する準備をしていたウガンダの歌の練習を始めた。すると、遠くに米粒のように小さく見える鳥が現れた。何と何とそれがオーストリッチだったのだ。私のテンションは一気にアップした。これでもかと言わんばかりに歌を熱唱した。その歌に釣られたのか、面白いように二頭のオーストリッチが私の方へ集まってきた。そして、ついには数頭が私の柵の目の前までやって来たのである。近くで見る彼らは2メーターを優に越えていた。ヤツの前足で蹴られたら私の命はないだろう。それくらいとてつもなく迫力があった。少ししてから、子供たちが続々とやってきた。その鳥を発見するや否や子供たちは一斉に駆け寄り、目を飛び出そうなくらい見開いて、まじまじとその巨大鳥を見ていた。ほんとに良かった。私にとってその鳥を見るよりも彼らの笑顔を見る方が何よりうれしかった。なぜ鳥が集まってきたのか、理由は私には分からない。私の思いが伝わったのか、それとも偶然なのか・・・どちらにせよ歌の練習もできたし、子供たちに鳥も見せることも出来たから結果オーライだ。これこそ本当の「一石二鳥」なのか?
 動物園見学の後、前から準備をしていた例の歌を子供たちに披露した。場所は湖の畔、バックにはかの有名なビクトリア湖、コーラスには波音といった具合である。うん、会場は抜群だ。後は私の声次第のようだ。精一杯の声で歌った。ルガンダ語の歌なので意味は分からず音のみで練習して望んだので本当に伝わるのか不安だったが、彼らの表情がその不安を吹き飛ばしてくれた。皆、目をきらきら輝かせながら笑顔で温かく僕の歌を聴いてくれていた。みんな手拍子をしてくれ、中には一緒に歌ってくれる子、リズムに乗って踊ってくれる子もいた。私の歌で彼らが喜んでくれたのなら何よりだ。帰りのバスでも子供たちはとても元気だった。どこか悲鳴にも似たような、興奮した声で叫んでいた。まるで日ごろの怒りや苦しみを訴えているかのように、私には聴こえた。そして同時に、この子供たちの将来を思った。
動物園見学の後、前から準備をしていた例の歌を子供たちに披露した。場所は湖の畔、バックにはかの有名なビクトリア湖、コーラスには波音といった具合である。うん、会場は抜群だ。後は私の声次第のようだ。精一杯の声で歌った。ルガンダ語の歌なので意味は分からず音のみで練習して望んだので本当に伝わるのか不安だったが、彼らの表情がその不安を吹き飛ばしてくれた。皆、目をきらきら輝かせながら笑顔で温かく僕の歌を聴いてくれていた。みんな手拍子をしてくれ、中には一緒に歌ってくれる子、リズムに乗って踊ってくれる子もいた。私の歌で彼らが喜んでくれたのなら何よりだ。帰りのバスでも子供たちはとても元気だった。どこか悲鳴にも似たような、興奮した声で叫んでいた。まるで日ごろの怒りや苦しみを訴えているかのように、私には聴こえた。そして同時に、この子供たちの将来を思った。
楽しかった遠足はこれで終わってしまった。おそらく、彼らにはまた単調で耐え難い日々が待っている。そんな毎日の中で、少しでもこの日の思い出が彼らに前を向いて歩く勇気や希望を与えてくれるなら、本当にありがたい。それは僕にとっても喜びであり、彼らもまた僕の背中を押してくれる。今はまだ学生で、何の技術も持っていない私が、彼らに出来る事と言えばこのくらいないのだから。
ウガンダ研修レポートVol.1はこちらからご覧になれます
The other day, the children and I decided to go to the zoo in Entebbe. On that day, I waited for the children to arrive; however, for some reason, I felt something was different. Yes, something was different.
"Oh!" I exclaimed in surprise. One boy came and he was wearing some clothes that made him look like some prince coming from a magical kingdom. He looked so cute!
I suppose that they had been anxiously waiting for the zoo excursion day. In their every day life, typically, they have no such opportunity to get out of their daily routine. Consequently, it is like they live the same day every day. One reason is that their families lack the economic resources for leisure activities. Usually, all they can do is to live their daily lives the best they can.
That is why I wanted to make the excursion day as joyful as possible with many smiling little faces that would remember that day for the rest of their lives.
We finally arrived at the zoo, and as the kids were looking around at the animals, I was waiting at “the place of the ostrich.”
After looking at the information, I learned that five ostriches could be seen in this area. However, I must say that these animals were roaming in a huge space (probably as big as a baseball field). If we think of Japanese zoos (which are not that small by international standards), this space would easily accommodate one entire zoo! Certainly, the space was out of proportion, especially because I could not see any ostriches anywhere.
A lot of nature, yes, but apparently only the vegetation was visible—an amazingly rich natural environment. But wait a second, this is something we would say for a national park but we were in a zoo!
The kids were so excited to come and see the animals, but there were none there. What on earth were the children supposed to look at? Vegetation? But that is what children see every day in Uganda.
I got impatient. I started to devise a plan in which I would dress like an ostrich, cross the fence and appear in front of the children when they came. Bad idea. They would realize sooner or later that I was not an ostrich but a human impostor.
When I was about to lose all my patience, G-d showed me what I was supposed to do. I remembered Mr. Mutsugoro (http://www.mutsugoro-animal-kingdom.com), who is very well known in Japan for his adventures with domestic and wild animals throughout the world. He used to say, "To get acquainted with an animal you have to become an animal."
In short, if you want the ostriches to be nice with you, you have to act like an ostrich.
I had no time to think. When the children came, I did not want their smiles to turn upside down. I had no doubt I had to do something, but to start with, I did not know anything about the sounds that ostriches make. Do ostriches cry? Anyway, I started to imitate the sound of "a bird". There was one guard there but I felt I had nothing to lose. The guard, who was staring at me, burst into laughter. It seemed that I was funny, but no bird was showing up at all. Not even a glimpse. After some time, I got tired and stopped making noises.
At least I knew how it felt to be a singing bird. Thank you Mr. Mutsugoro.
Well, I tried as hard as I could, but my efforts were useless. I needed something in case I had to comfort the children so I decided to practice a Ugandan song that I had been learning by heart without their noticing.
Just then, something showed up in the distance looking as small as a grain of rice. An ostrich! I was relieved. Despite this, I continued singing fervently. I was absorbed in the song, when suddenly two ostriches ran in my direction. Then those two and other ostriches came closer to the fence. At last! Looking closely, they were not less than 2 meters high.
It was just at that moment that the children started to come. As soon as they saw the birds, they ran all at once, their eyes were wide open and looking at the creatures with amazement.
I do not know the exact reason why the birds suddenly appeared. Was it because my pleas were heard? Anyhow, I was able to practice the song, and most importantly, I could see the long awaited smiling faces.
After looking at the animals, I announced to the kids I wanted to sing the song I had been practicing. The stage was all set. What could be better than a place at the edge of the famous Lake Victoria? The chorus could well be the sound of the water. Well, I sang as fervently as possible. Since the song is written in a language called Luganda, which I cannot understand, I just tried to memorize the sounds of the words. For this reason I could not relax, but to my surprise, the song was welcomed warmly with smiles and shining eyes.
All the kids were clapping their hands, some kids sang with me and some others danced to the rhythm of the music. The important thing was that all this filled their hearts with joy and happiness.
The kids were in a very good mood in the bus on our way back to the village. In the bus, I heard something like a cry of pain coming from somewhere. It seemed to me like one of those cries of anger and suffering. At the same time, I was thinking about the future of these kids.
The excursion was pleasant and had finished well. Maybe the unbearable monotony of their lives was awaiting them but I wished that the memories of that day could bring the courage and hope that they need to face the reality of every day.
Masashi is a BS student of production systems engineering at Toyohashi University of Technology. He is spending a year in Uganda working as a volunteer helping children that became orphans as a result of AIDS. He can be reached at masashi_haruna_world_ofmarfy_2_13<at>hotmail.co.jp. Translated from Japanese by Rafael Batres. Revised and corrected by David Levin.
<at> = @
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 時が経つのは早いもので、ウガンダに来てもう二ヶ月が過ぎようとしている。少しずつこちらの生活にも慣れ、ウガンダライフを楽しめるようになってきた今日この頃だ。今月は子供たちにとって楽しみでたまらないイベント「アウティング(遠足)」があり、たくさんの子供たちを連れてエンテベの動物園へ行った。今回はその事を書こうと思う。
時が経つのは早いもので、ウガンダに来てもう二ヶ月が過ぎようとしている。少しずつこちらの生活にも慣れ、ウガンダライフを楽しめるようになってきた今日この頃だ。今月は子供たちにとって楽しみでたまらないイベント「アウティング(遠足)」があり、たくさんの子供たちを連れてエンテベの動物園へ行った。今回はその事を書こうと思う。当日の朝集合場所に行き、子供たちを待っていると、続々と子供たちがやってきた。しかし、何かいつもと雰囲気が違う気がした。確かに何かが違う。でも、これと言って浮かんでこなかった。すると、一人の男の子が来て私はハッとした。「おぉ!」思わず声を上げた。彼はどこかの国の王子様っぽい、「これぞ我が家のザ正装!」と言わんばかりの洋服を身にまといやって来たのである。なんとも言えない愛くるしさだ。思わず写真を撮ってしまった私である。そう、見渡すと子供たちはみんないつもより格段に綺麗な服でやって来ていたのである。中には「えっ?ディズニーのパレードから来たんですか?!」と聞きたくなるようなドレスを着た女の子もいた。子供たちのこの日に寄せる思いは相当だ。彼らを見るとこの遠足をどれほど楽しみにしていたのか言われなくてもビシバシ伝わってきた。彼らの日常の中では、こんな非日常的な楽しみは望んでも得られるはずも無く、毎日毎日同じような生活を強いられている。彼らの家には余暇を楽しむほどのお金は無い。日々の生活をしていくだけで精一杯だ。だからこそ私はこのアウティングを少しでも楽しいものにして、子供たちの笑顔の花をたくさん咲かせてやろうと、あいつらの一生の思い出に残る最高の日にしてやろうと、心から思った。
 動物園に着き、子供たちが動物を見て回っている間、私はチェックポイントである「オーストリッチ」と言うダチョウに似たでかい鳥の所で子供たちが来るのを待っていた。聞くと、やたらと広い(おそらく野球場くらいある)敷地の中にたった5頭しかいないらしい。日本の動物園事情を考えるとここだけで一つの動物園が出来そうである。・・・どう考えても無駄に広い。そう思うのは私が日本人だからだろうか?いや、おそらく違う。なぜならどこにもオーストリッチがいないからだ。そこにはただ豊かな自然が広がっていた。「わぁ、すごい!さすがウガンダ!やっぱり自然が豊かやなぁ〜。・・・違う違う。」国立公園ならまだ分かるが、ここは動物園だ。子供たちが動物を見るためにわくわく胸を弾ませやって来る。それなのに何もいないのである。子供たちはいったい何を見ればいいのだろうか?ウガンダの自然?そんなの子供らは毎日見ている。私はあせった。いっそのこと私が柵の中に入ってオーストリッチ風に現れようかとも思った。しかしそれはまずい・・・それではオーストリッチではなく「ヒト」だ。まぁ彼らにとって日本人も珍しいからいいかなぁ・・・?いや全然ダメだ。焦っているちょうどその時に、私に神が舞い降りた。私は日本人なら誰でも知っているであろう、ムツゴロウさんを思い出したのだ。彼は言っていた、「動物と仲良くなりたければ動物になれ。」と。つまり「オーストリッチと仲良くなりたければオーストリッチになれ。」という事だろう。私に考える暇など無かった。いつ子供たちが来てもおかしくない。しかし、彼らの笑顔が曇るのだけはどうしても見たくない。私に迷いは無かった。オーストリッチの鳴き声など知らないが(そもそも鳴くのか?)私の知っている限りの鳥風の鳴き声を連発した。幸いそこには警備員の方しかいなかったので、私に失うものは何も無かった。それを見て警備員の方は爆笑していたのだが・・・。しかし一向に鳥は現れない。気配すらない。少し経ち、私は鳴きつかれやめてしまった。何となく鳥の鳴く気持ちが分かった気がする。「ありがとうムツゴロウさん。僕は精一杯やったよ。でも僕には無理だったよ、オーストリッチ・・・。」少し落ち込んだが、くよくよしても仕方ないと思い、私は子供たちに内緒で、披露する準備をしていたウガンダの歌の練習を始めた。すると、遠くに米粒のように小さく見える鳥が現れた。何と何とそれがオーストリッチだったのだ。私のテンションは一気にアップした。これでもかと言わんばかりに歌を熱唱した。その歌に釣られたのか、面白いように二頭のオーストリッチが私の方へ集まってきた。そして、ついには数頭が私の柵の目の前までやって来たのである。近くで見る彼らは2メーターを優に越えていた。ヤツの前足で蹴られたら私の命はないだろう。それくらいとてつもなく迫力があった。少ししてから、子供たちが続々とやってきた。その鳥を発見するや否や子供たちは一斉に駆け寄り、目を飛び出そうなくらい見開いて、まじまじとその巨大鳥を見ていた。ほんとに良かった。私にとってその鳥を見るよりも彼らの笑顔を見る方が何よりうれしかった。なぜ鳥が集まってきたのか、理由は私には分からない。私の思いが伝わったのか、それとも偶然なのか・・・どちらにせよ歌の練習もできたし、子供たちに鳥も見せることも出来たから結果オーライだ。これこそ本当の「一石二鳥」なのか?
動物園に着き、子供たちが動物を見て回っている間、私はチェックポイントである「オーストリッチ」と言うダチョウに似たでかい鳥の所で子供たちが来るのを待っていた。聞くと、やたらと広い(おそらく野球場くらいある)敷地の中にたった5頭しかいないらしい。日本の動物園事情を考えるとここだけで一つの動物園が出来そうである。・・・どう考えても無駄に広い。そう思うのは私が日本人だからだろうか?いや、おそらく違う。なぜならどこにもオーストリッチがいないからだ。そこにはただ豊かな自然が広がっていた。「わぁ、すごい!さすがウガンダ!やっぱり自然が豊かやなぁ〜。・・・違う違う。」国立公園ならまだ分かるが、ここは動物園だ。子供たちが動物を見るためにわくわく胸を弾ませやって来る。それなのに何もいないのである。子供たちはいったい何を見ればいいのだろうか?ウガンダの自然?そんなの子供らは毎日見ている。私はあせった。いっそのこと私が柵の中に入ってオーストリッチ風に現れようかとも思った。しかしそれはまずい・・・それではオーストリッチではなく「ヒト」だ。まぁ彼らにとって日本人も珍しいからいいかなぁ・・・?いや全然ダメだ。焦っているちょうどその時に、私に神が舞い降りた。私は日本人なら誰でも知っているであろう、ムツゴロウさんを思い出したのだ。彼は言っていた、「動物と仲良くなりたければ動物になれ。」と。つまり「オーストリッチと仲良くなりたければオーストリッチになれ。」という事だろう。私に考える暇など無かった。いつ子供たちが来てもおかしくない。しかし、彼らの笑顔が曇るのだけはどうしても見たくない。私に迷いは無かった。オーストリッチの鳴き声など知らないが(そもそも鳴くのか?)私の知っている限りの鳥風の鳴き声を連発した。幸いそこには警備員の方しかいなかったので、私に失うものは何も無かった。それを見て警備員の方は爆笑していたのだが・・・。しかし一向に鳥は現れない。気配すらない。少し経ち、私は鳴きつかれやめてしまった。何となく鳥の鳴く気持ちが分かった気がする。「ありがとうムツゴロウさん。僕は精一杯やったよ。でも僕には無理だったよ、オーストリッチ・・・。」少し落ち込んだが、くよくよしても仕方ないと思い、私は子供たちに内緒で、披露する準備をしていたウガンダの歌の練習を始めた。すると、遠くに米粒のように小さく見える鳥が現れた。何と何とそれがオーストリッチだったのだ。私のテンションは一気にアップした。これでもかと言わんばかりに歌を熱唱した。その歌に釣られたのか、面白いように二頭のオーストリッチが私の方へ集まってきた。そして、ついには数頭が私の柵の目の前までやって来たのである。近くで見る彼らは2メーターを優に越えていた。ヤツの前足で蹴られたら私の命はないだろう。それくらいとてつもなく迫力があった。少ししてから、子供たちが続々とやってきた。その鳥を発見するや否や子供たちは一斉に駆け寄り、目を飛び出そうなくらい見開いて、まじまじとその巨大鳥を見ていた。ほんとに良かった。私にとってその鳥を見るよりも彼らの笑顔を見る方が何よりうれしかった。なぜ鳥が集まってきたのか、理由は私には分からない。私の思いが伝わったのか、それとも偶然なのか・・・どちらにせよ歌の練習もできたし、子供たちに鳥も見せることも出来たから結果オーライだ。これこそ本当の「一石二鳥」なのか? 動物園見学の後、前から準備をしていた例の歌を子供たちに披露した。場所は湖の畔、バックにはかの有名なビクトリア湖、コーラスには波音といった具合である。うん、会場は抜群だ。後は私の声次第のようだ。精一杯の声で歌った。ルガンダ語の歌なので意味は分からず音のみで練習して望んだので本当に伝わるのか不安だったが、彼らの表情がその不安を吹き飛ばしてくれた。皆、目をきらきら輝かせながら笑顔で温かく僕の歌を聴いてくれていた。みんな手拍子をしてくれ、中には一緒に歌ってくれる子、リズムに乗って踊ってくれる子もいた。私の歌で彼らが喜んでくれたのなら何よりだ。帰りのバスでも子供たちはとても元気だった。どこか悲鳴にも似たような、興奮した声で叫んでいた。まるで日ごろの怒りや苦しみを訴えているかのように、私には聴こえた。そして同時に、この子供たちの将来を思った。
動物園見学の後、前から準備をしていた例の歌を子供たちに披露した。場所は湖の畔、バックにはかの有名なビクトリア湖、コーラスには波音といった具合である。うん、会場は抜群だ。後は私の声次第のようだ。精一杯の声で歌った。ルガンダ語の歌なので意味は分からず音のみで練習して望んだので本当に伝わるのか不安だったが、彼らの表情がその不安を吹き飛ばしてくれた。皆、目をきらきら輝かせながら笑顔で温かく僕の歌を聴いてくれていた。みんな手拍子をしてくれ、中には一緒に歌ってくれる子、リズムに乗って踊ってくれる子もいた。私の歌で彼らが喜んでくれたのなら何よりだ。帰りのバスでも子供たちはとても元気だった。どこか悲鳴にも似たような、興奮した声で叫んでいた。まるで日ごろの怒りや苦しみを訴えているかのように、私には聴こえた。そして同時に、この子供たちの将来を思った。楽しかった遠足はこれで終わってしまった。おそらく、彼らにはまた単調で耐え難い日々が待っている。そんな毎日の中で、少しでもこの日の思い出が彼らに前を向いて歩く勇気や希望を与えてくれるなら、本当にありがたい。それは僕にとっても喜びであり、彼らもまた僕の背中を押してくれる。今はまだ学生で、何の技術も持っていない私が、彼らに出来る事と言えばこのくらいないのだから。
ウガンダ研修レポートVol.1はこちらからご覧になれます
(以下、英訳文:生産システム工学系准教授 バトレス ラファエル, 人文・社会工学系准教授 レビン デイヴィッド)
A Day at the Entebbe Zoo
Masashi Haruna, June 2008
Time flies, and it is going to be two months since I came to Uganda. I am still getting used to the life in this land but there are already some meaningful moments that I would like to share with you.
The other day, the children and I decided to go to the zoo in Entebbe. On that day, I waited for the children to arrive; however, for some reason, I felt something was different. Yes, something was different.
"Oh!" I exclaimed in surprise. One boy came and he was wearing some clothes that made him look like some prince coming from a magical kingdom. He looked so cute!
Soon after, I realized that the other children were also coming dressed in beautiful garments. There was this little girl with such a cute dress that I felt like asking her, "Did you guys escape from a fairy-tale parade?"
I suppose that they had been anxiously waiting for the zoo excursion day. In their every day life, typically, they have no such opportunity to get out of their daily routine. Consequently, it is like they live the same day every day. One reason is that their families lack the economic resources for leisure activities. Usually, all they can do is to live their daily lives the best they can.
That is why I wanted to make the excursion day as joyful as possible with many smiling little faces that would remember that day for the rest of their lives.
We finally arrived at the zoo, and as the kids were looking around at the animals, I was waiting at “the place of the ostrich.”
After looking at the information, I learned that five ostriches could be seen in this area. However, I must say that these animals were roaming in a huge space (probably as big as a baseball field). If we think of Japanese zoos (which are not that small by international standards), this space would easily accommodate one entire zoo! Certainly, the space was out of proportion, especially because I could not see any ostriches anywhere.
A lot of nature, yes, but apparently only the vegetation was visible—an amazingly rich natural environment. But wait a second, this is something we would say for a national park but we were in a zoo!
The kids were so excited to come and see the animals, but there were none there. What on earth were the children supposed to look at? Vegetation? But that is what children see every day in Uganda.
I got impatient. I started to devise a plan in which I would dress like an ostrich, cross the fence and appear in front of the children when they came. Bad idea. They would realize sooner or later that I was not an ostrich but a human impostor.
When I was about to lose all my patience, G-d showed me what I was supposed to do. I remembered Mr. Mutsugoro (http://www.mutsugoro-animal-kingdom.com), who is very well known in Japan for his adventures with domestic and wild animals throughout the world. He used to say, "To get acquainted with an animal you have to become an animal."
In short, if you want the ostriches to be nice with you, you have to act like an ostrich.
I had no time to think. When the children came, I did not want their smiles to turn upside down. I had no doubt I had to do something, but to start with, I did not know anything about the sounds that ostriches make. Do ostriches cry? Anyway, I started to imitate the sound of "a bird". There was one guard there but I felt I had nothing to lose. The guard, who was staring at me, burst into laughter. It seemed that I was funny, but no bird was showing up at all. Not even a glimpse. After some time, I got tired and stopped making noises.
At least I knew how it felt to be a singing bird. Thank you Mr. Mutsugoro.
Well, I tried as hard as I could, but my efforts were useless. I needed something in case I had to comfort the children so I decided to practice a Ugandan song that I had been learning by heart without their noticing.
Just then, something showed up in the distance looking as small as a grain of rice. An ostrich! I was relieved. Despite this, I continued singing fervently. I was absorbed in the song, when suddenly two ostriches ran in my direction. Then those two and other ostriches came closer to the fence. At last! Looking closely, they were not less than 2 meters high.
It was just at that moment that the children started to come. As soon as they saw the birds, they ran all at once, their eyes were wide open and looking at the creatures with amazement.
Everything was good. I was happy when the birds showed up, but I was even happier to see the smiling faces full of excitement.
I do not know the exact reason why the birds suddenly appeared. Was it because my pleas were heard? Anyhow, I was able to practice the song, and most importantly, I could see the long awaited smiling faces.
After looking at the animals, I announced to the kids I wanted to sing the song I had been practicing. The stage was all set. What could be better than a place at the edge of the famous Lake Victoria? The chorus could well be the sound of the water. Well, I sang as fervently as possible. Since the song is written in a language called Luganda, which I cannot understand, I just tried to memorize the sounds of the words. For this reason I could not relax, but to my surprise, the song was welcomed warmly with smiles and shining eyes.
All the kids were clapping their hands, some kids sang with me and some others danced to the rhythm of the music. The important thing was that all this filled their hearts with joy and happiness.
The kids were in a very good mood in the bus on our way back to the village. In the bus, I heard something like a cry of pain coming from somewhere. It seemed to me like one of those cries of anger and suffering. At the same time, I was thinking about the future of these kids.
The excursion was pleasant and had finished well. Maybe the unbearable monotony of their lives was awaiting them but I wished that the memories of that day could bring the courage and hope that they need to face the reality of every day.
Masashi is a BS student of production systems engineering at Toyohashi University of Technology. He is spending a year in Uganda working as a volunteer helping children that became orphans as a result of AIDS. He can be reached at masashi_haruna_world_ofmarfy_2_13<at>hotmail.co.jp. Translated from Japanese by Rafael Batres. Revised and corrected by David Levin.
<at> = @